近年では、企業における研修のあり方が大きく変化しています。従来の対面形式に加え、オンライン研修やeラーニングなど、時間や場所にとらわれずに学習できる環境が整いつつあります。そのなかでも、注目を集めているのが「研修動画」です。
本記事では、研修動画の制作ポイントと活用メリットを解説するとともに、具体的な事例7選をご紹介します。研修動画を検討している方、効果的な研修動画の制作方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、教育・研修動画の豊富な制作実績があります。動画制作を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。
ムビサクの教育・研修動画の制作について詳しく知りたい方はこちら
- 研修動画の事例と制作のポイント
- 研修動画を活用するメリット・デメリット
- 研修動画を外注する費用相場と安く抑える方法
目次
動画制作でこんなお悩みありませんか?
- 動画制作を考えているがどうすればよいかわからない
- 急いで動画を作りたいが方法がわからない
- 高品質な動画を制作したいが自社では難しい…
\ スピーディーに高品質な動画を作るならムビサク /
無料で相談・問い合わせる研修動画とはどんな動画?

研修動画とは、従来の対面形式で行われる研修を、教育コンテンツとしてオンラインで配信する学習動画の新しい形式です。受講者は、パソコンやスマホなどの端末を使って、いつでもどこでも研修を受けることができます。
近年では、企業における研修のあり方が大きく変化しており、研修動画は社員教育をアップデートする革新的な学習ツールとして、注目を集めています。
研修動画は、オンライン研修やeラーニングで活用されています。
オンライン研修とは、インターネットを介して受講する研修の総称です。オンライン研修のメリットやデメリットについては、以下の記事も参考にしてください。
また、eラーニングでは、自動で学習コンテンツの管理を行ってくれる「LMS(学習管理システム)」と呼ばれるシステムを用いて、受講者の学習管理も可能です。eラーニング向けの動画制作については、こちらもご覧ください。
研修動画の事例7選

効果的な研修動画を制作するには、他社の成功事例を参考にすることもおすすめです。ここでは、以下の企業における研修動画の事例を紹介します。
- セルプロモート株式会社
- 三ツ星ベルト株式会社
- 開隆堂出版株式会社
- 株式会社インヴァランス
- Shopify Japan 株式会社
- 東京都専修学校各種学校協会
- ニッタ・デュポン株式会社
セルプロモート株式会社
事例:採用活動におけるオンボーディング動画
IT人材の育成とキャリアプランの形成に力を注ぐセルプロモート株式会社のオンボーディング動画です。
オンボーディング(on-boarding)とは、「乗り物に乗っている」という意味に由来しています。新卒や中途で入社した新しい仲間が、会社やチームに慣れてもらうようにするための研修のことです。
会社説明会やエンジニアの中途採用の面接時に流す動画として、入社後の流れや人事評価の仕組みについて、詳しく解説しています。
言葉では表現しづらい人事制度の仕組みについて、シンプルなアニメーションを活用している点がポイントです。
三ツ星ベルト株式会社
事例:部品紹介を英語翻訳した多言語動画
自動車、産業機械用の伝動ベルトや搬送ベルトの製造・販売を行う三ツ星ベルト株式会社の英語動画です。シンガポール、インドネシア、タイ、中国、インド、ベトナムなどのアジア圏だけでなく、アメリカ、ドイツなどの北米、欧州にも営業拠点や生産拠点を有しています。
そのため、グローバルな展開を見越して多言語で部品の機能を解説する動画を制作しています。
動画では、PCとスマホの両方で視聴されることを想定して、BGMを加えて視聴維持率の向上を狙っている点がポイントです。
開隆堂出版株式会社
事例:中学生向け英語教材の解説動画
開隆堂出版株式会社が出版する、令和7年度用の中学校英語の教科書である「Sunshine English Course」の内容を解説する動画です。
視聴者は、学校や教育委員会の教科書採択員の方ということでした。そのため、男性と女性のキャラクターが掛け合うかたちで、楽しくポップでありながらも、説得力のある動画にしている点がポイントです。
また、教科書の内容を流すだけではなく、カリキュラムについても図やアニメーションを活用することで、イメージしやすい動画に仕上げています。
株式会社インヴァランス
事例:YouTubeチャンネル掲載用の教育・講座動画
不動産管理や資産運用を支援する株式会社インヴァランスの講座動画です。この動画は、社内向けの研修動画ではなく、YouTubeチャンネル「Z世代のマネー学」で配信されている、社外向けの研修コンテンツです。
想定される視聴者を若年層の「Z世代」として、不動産に限らず、投資に関する知識を面白く学べる動画になっています。
7~8分の動画ですが、最後まで飽きることのないように、キャラクターを用いたポップで分かりやすい映像に仕上げている点が特徴です。
Shopify Japan 株式会社
事例:パートナー向けインストラクション動画
Shopify Japan 株式会社が提供する、サブスクリプション型で、誰もがすぐにネットショップを開始して商品を販売できるソフトウェアである「Shopify」のインストラクション動画です。
インストラクション動画とは、製品の仕組みや使い方を説明する動画のことです。この動画では、Shopifyを利用してストアオーナーになっている方に向けて、管理画面の使い方を、実際のPC画面をもとに解説しています。
インストラクション動画では、できるだけシンプルにすることが重要です。そのため、必要な情報を精査して、分かりやすく伝わる構成に仕上げています。
東京都専修学校各種学校協会
事例:専修学校と専門学校の解説動画
東京都の専修学校・各種学校を代表する団体である、東京都専修学校各種学校協会の動画です。高校生や保護者に向けて、専修学校と専門学校の違いを分かりやすく説明しています。
学校紹介という教育関連の内容のため、全体を通して板書(ノート)をイメージした背景にした点がポイントです。シンプルすぎず、背景が邪魔をして見えづらいことがないように工夫しています。
また、専門学校に興味を持ってもらう高校生が増えるように、飽きのこないアニメーション動画で仕上げています。
ニッタ・デュポン株式会社
事例:周年記念式典に向けたロゴアニメーション
研磨パッドやスラリー、バッキング材、コンディショナーなどの工業製品を取り扱う企業である、ニッタ・デュポン株式会社の社内イベント用の動画です。
ニッタ・デュポン株式会社では、創業40周年を記念したリブランディングとして、ロゴマークを刷新しました。動画では、社員向けの周年記念イベントで、ロゴに込められて思いや、企業の掲げるビジョンを紹介しています。
従業員に対して、企業理念やビジョンを共有する研修やイベントを、インナーブランディングと呼びます。従業員が自社やロゴマークに愛着を持つことで、働きがいやモチベーションのアップにもつながります。
なお、インナーブランディングの成功事例については、以下の記事も参考にしてください。
動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、社員向けのインナーブランディングから、講演会、セミナー、マニュアルまで幅広い教育・研修動画の制作実績があります。
また、無料相談も承っていますので、ぜひ一度お問い合わせください。
研修動画を制作する際のポイント
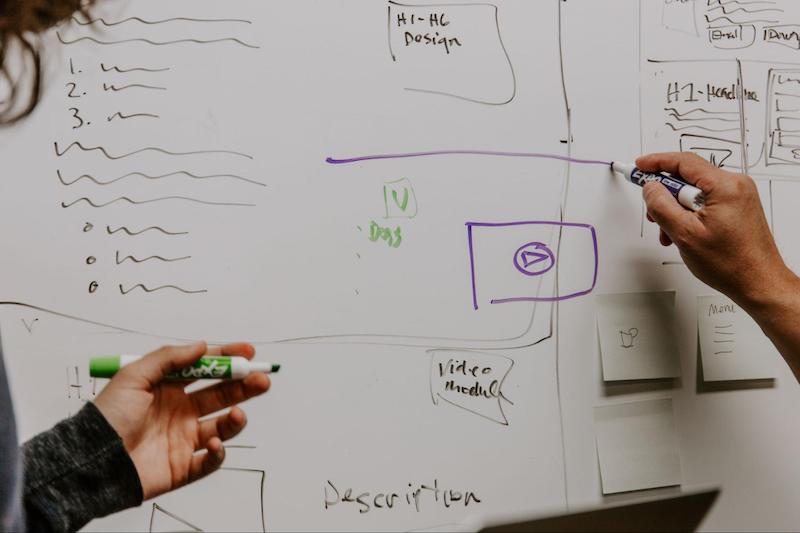
研修動画を制作する際にはポイントがあります。ここでは、以下のポイントを紹介します。
- 研修の目的とターゲットを明確にする
- メリハリのある動画構成にする
- はっきりとしたナレーションを加える
- 専門用語にはテロップをつける
- スマホでも視聴できる動画にする
研修の目的とターゲットを明確にする
研修動画を制作する前に、まず「何を伝えたいのか」「誰に伝えたいのか」を明確にすることが重要です。目的とターゲットによって、動画の内容や構成が大きく変わってきます。
例えば、研修には以下のような目的があります。
- 新入社員研修:会社の基本情報や業務内容を理解してもらう
- 商品知識研修:新商品の機能や使い方を説明する
- 業務スキルアップ研修:具体的な業務手順やテクニックを指導する
- 安全教育:事故や災害の防止に関する知識や意識を高める
また、ターゲットによっても、研修動画の内容は異なります。例えば、研修動画のターゲットには、以下のような人物が挙げられます。
- 新入社員
- 既存社員
- 特定の部署の社員
- マネジメント層
- パート・アルバイト
- お客様
- 生徒
なお、目的やターゲットを明確にするには、研修動画の企画書を作成しておくこともおすすめです。企画書の作り方については、以下の記事も参考にしてください。
メリハリのある動画構成にする
視聴者の集中力を維持するためには、メリハリのある動画構成にすることが重要です。単調な内容が続くと、視聴者は飽きてしまい、学習効果が低下してしまいます。
具体的には、以下の構成がおすすめです。
- オープニング:研修の内容を簡単に紹介する
- 本編:セクションを短く区切って見やすくする
- 重要なポイント:効果音やテロップで強調して説明する
- クロージング:研修内容をまとめ今後の行動を促す
オープニングでは、視聴者の興味を引くような印象的な映像や音楽を使用してみることがよいでしょう。また、本編では、複雑な内容は図表やイラストなどを活用して分かりやすく説明し、重要なポイントは強調して視聴者の印象に残るようにします。そして、クロージングでは、研修で学んだことを振り返り、今後の行動を促すメッセージを伝えましょう。
なお、動画構成の考え方については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
はっきりとしたナレーションを加える
ナレーションは、動画の内容を理解するための重要な要素です。聞き取りやすく、分かりやすいナレーションを心がけましょう。
例えば、ナレーションを収録する際に、以下の点を意識してください。
- ゆっくりと話す
- 滑舌を良くする
- 抑揚をつける
- 専門用語はわかりやすく説明する
ゆっくりと話すことで、視聴者は内容を理解しやすくなります。ただし、ゆっくりとしたテンポでは、受講者が飽きてしまうこともあります。
そのため、滑舌を良くすることで、聞き取りやすくしてみることもおすすめです。また、抑揚をつけることで、視聴者の集中力を維持することができます。
加えて、専門用語が出てくる場合は、分かりやすく説明することで、受講者に伝わる効果的な研修になります。
専門用語にはテロップをつける
研修動画の内容に、専門用語が出てくる場合は、テロップをつけて補足説明を加えましょう。こうすることで、視聴者の理解度を高めることができます。
例えば、以下のような編集を加えてみることがおすすめです。
- 専門用語を太字にする
- 専門用語の意味を簡単に説明する
- 図表やイラストを活用する
専門用語を太字にすることで、視聴者の視線を自然に引きつけることができます。しかし、あまり馴染みのない専門用語が多くなると、受講者の集中力の低下につながってしまいます。
そのため、専門用語の意味を簡単に説明することで、視聴者が内容を理解しやすくしておきましょう。注釈を加えたり、図表やイラストを活用したりすることで、専門用語をより分かりやすく伝えることもできます。
スマホでも視聴できる動画にする
近年、スマホで動画を視聴する人が増えています。企業によっては、社員向けの携帯電話として、スマホを支給していることもあるでしょう。そのため、スマホでも視聴できるよう、適切なサイズや構成で動画を制作する必要があります。
例えば、スマホ向けの動画には、以下のような点を意識しましょう。
- 動画の長さを短くする
- 字幕やテロップをつける
- モバイル対応の動画配信サイトを利用する
スマホで視聴する際には、通勤電車や休憩中など、スキマ時間に視聴されることもあります。そのため、動画の長さを短くすることで、視聴者は最後まで集中して視聴することができます。
また、字幕やテロップをつけることで、音声がない環境でも視聴することができます。加えて、モバイル対応の動画配信サイトを利用することで、スマホで視聴しやすいようにすることができます。
なお、スマホ向けの動画配信として、縦型動画に対応したYouTubeショートやTikTokが挙げられます。YouTubeショートでの動画配信については、以下の記事でも詳しく解説しています。
研修動画を活用するメリット

研修動画を企業が活用するメリットには、主に以下のようなものがあります。
- スキマ時間に効率よく学べる
- 講師による質のバラつきがない
- 研修にかかるコストを削減できる
ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
スキマ時間に効率よく学べる
スキマ時間に効率よく学べる点は研修動画のメリットです。研修動画は、通勤時間や休憩時間など、スキマ時間に視聴することができます。忙しい現代人にとって、まとまった時間を確保して研修を受けるのは難しいものです。しかし、研修動画であれば、短時間でも効率的に学習することができます。
また、繰り返し視聴できるという点も大きなメリットです。理解度が低い部分があれば、何度でも繰り返し視聴することで、理解を深めることができます。
研修動画のメリットやポイントについては、こちらの記事も参考にしてください。
講師による質のバラつきがない
講師による質のバラつきがない点も研修動画を活用するメリットです。対面形式の研修では、講師によって教え方や内容に差が生じてしまうことがあります。しかし、研修動画であれば、すべての受講者が同じ内容を同じように学ぶことができます。
また、研修動画は、専門知識をもとに制作されるため、質の高い学習内容を安定的に提供することができます。また、テロップやアニメーションを加えた動画編集によって、分かりやすく見やすい映像に仕上げることが可能です。
研修にかかるコストを削減できる
研修動画を制作することで、講師費や会場費などの研修にかかるコストを驚異的に削減することができます。従来の対面形式の研修では、講師の交通費や宿泊費、会場の設営・撤去費用、教材印刷費用など、様々なコストが発生します。しかし、研修動画であれば、これらのコストを大幅に削減することができます。
さらに、交通費や宿泊費などの受講者にかかる負担も軽減できます。受講者が遠隔地にいる場合、交通費や宿泊費が研修参加の大きな壁となることがあります。しかし、研修動画であれば、受講者は自宅やオフィスなど、好きな場所で学習することができます。
研修動画を活用するデメリット

研修動画は効果的であり、多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。ここでは、以下のデメリットについて、解説します。
- 双方向のコミュニケーションができない
- 受講にはインターネット環境が必要
- 研修動画の制作に時間がかかる
双方向のコミュニケーションができない
研修動画のデメリットは、講師やと受講者や、受講者同士の双方向的なコミュニケーションが難しい点です。対面研修であれば、講師の表情や声のトーン、受講者の反応などを参考に、理解度を確認したり、質問に答えたりすることができます。
しかし、動画の場合は一方通行の情報伝達となるため、受講者の理解度を正確に把握することが難しく、質問や疑問があってもその場で解決できないという課題があります。
とくに、演習やグループワークなど、参加者同士の交流が重要となる研修内容の場合、動画形式では効果が薄れてしまう可能性があります。また、モチベーション維持の点でも、双方向のコミュニケーションによる刺激がないため、受講者によっては集中力が途切れてしまうことも懸念されます。
受講にはインターネット環境が必要
研修動画を受講するには、インターネット環境が必要となります。以前も研修動画はありましたが、社内のテレビモニターで閲覧する「研修ビデオ」が主流でした。
しかし、現在では、オンライン上で共有された動画教材を用いたeラーニングが増えてきています。そのため、社内ネットワークやWi-Fi環境が整っていない場所では視聴できず、受講者の環境によっては制約が生じる可能性があります。
また、動画データの容量が大きい場合、モバイル通信で視聴しようとすると通信制限に引っかかってしまう可能性もあります。さらに、通信環境が不安定だと動画の読み込みが遅くなったり、途中で途切れてしまったりするなど、視聴ストレスが溜まる可能性もあります。
なお、YouTubeを研修で使用したい方も多いのではないでしょうか。以下の記事では、YouTubeの動画を社内研修に使う際の注意点を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
研修動画の制作に時間がかかる
研修動画を制作するには、企画、撮影、編集など、多くの時間と労力が必要です。とくに、高品質な動画を制作しようとすると、専門的な知識やスキルが必要となります。また、講師の選定や台本作成、撮影場所の設定など、事前に準備しておくべきこともたくさんあります。
さらに、動画の長さや内容によっては、複数の撮影日が必要になる場合もあります。このように、研修動画の制作には想像以上に時間がかかることを認識しておくことが重要です。
なお、動画編集にかかる時間については、以下の記事もご覧ください。
研修動画を外注する際の費用相場

研修動画を外注する際の費用相場は、一般的に20万円~100万円程度です。すでに自社で撮影した動画の編集のみであれば、動画制作にかかる工数を抑えることができるため、費用相場は2万円~20万円程度が一般的です。
ただし、動画の長さや内容、撮影の有無によっても異なります。
以下に、研修動画の制作における、1分・3分・5分・10分・30分の動画尺と一般的な費用相場をまとめて紹介します。
| 動画尺(動画の長さ) | 費用相場 |
|---|---|
| 1分 | 50万円~100万円 |
| 3分 | 60万円~120万円 |
| 5分 | 70万円~150万円 |
| 10分 | 80万円~150万円 |
| 30分 | 100万円~200万円 |
なお、研修動画の費用相場については、こちらの記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
研修動画の外注費用を安く抑える方法
研修動画の外注費用を安く抑えるためには、以下の点に注意しましょう。
- 動画の長さや内容を明確にする
- 自社にある素材を活用する
- 撮影のないアニメーション動画にする
動画の長さや内容を明確にする
漠然としたイメージで制作会社に依頼すると、高額な見積もりになってしまう可能性があります。具体的な尺数や伝えたい内容を事前に決めておくことで、制作会社も無駄な工数を省き、予算にあった研修動画を制作することができます。
自社にある素材を活用する
研修資料や過去の研修動画など、自社ですでに用意されている素材を活用しましょう。資料をそのまま動画化するのではなく、必要な部分だけを抽出し、効果的な構成に編集することで、制作にかかるコストを削減することができます。
撮影のないアニメーション動画にする
講師を招いて撮影をする実写動画は、どうしても時間がかかり、費用も高くなります。そこで、撮影のないアニメーション動画を検討してみてはいかがでしょうか。アニメーション動画であれば、場所や時間を選ばずに制作することができ、複雑な動きや抽象的な概念も表現しやすくなります。
もちろん、専門知識やスキルが必要となるため、自社で制作するのが難しい場合は、制作会社に依頼するのも良いでしょう。
動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、アニメーション動画や実写動画を用いた、教育・研修動画の豊富な制作実績があります。
また、無料相談も承っていますので、ぜひ一度お問い合わせください。
研修動画の事例に関するよくあるご質問
研修動画の事例についてのご質問はかなり多くいただきます。その中から、頻度の高いものへの回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
動画研修とは何ですか?
- 動画研修とは、音と動きで構成された映像を用いた研修形式のひとつです。オンライン研修やeラーニングとも呼ばれます。講師が説明する姿を事前に撮影した動画を用いる研修や、スライドに動きやナレーションを加えた動画を用いた研修などさまざまなものがあります。
社内研修で動画配信をするメリットは?
- 社内研修で動画配信をするメリットは、いつでもどこでも視聴できる点です。従来の社内研修では、本社の会議室や講演会場に従業員が足を運ぶ必要がありました。しかし、動画配信をすることで、実際に足を運ぶ必要がなく、支店や自宅からでも研修に参加することができます。
なぜ研修が必要なのですか?
- 研修は、企業が現代社会で生き残るために、従業員の能力開発がとして必要不可欠です。研修は、知識・スキルの習得、業務効率向上、モチベーション向上、コミュニケーション能力向上、安全意識向上など、重要な役割を果たします。企業が研修へ投資することで、従業員の成長と組織全体の競争力強化につながります。
まとめ

近年では、企業における研修のあり方が大きく変化しており、研修動画は社員教育をアップデートする革新的な学習ツールとして、注目を集めています。
効果的な研修動画を制作するには、他社の成功事例を参考にすることがおすすめです。目的やターゲットを明確にして、メリハリのある構成で、研修コンテンツを作っていきましょう。
研修動画は、自社で制作することもできますが、動画制作のできる人材リソースが必要であり、スキルや技術も必要不可欠です。そのため、動画制作会社に外注してみることもおすすめです。
動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、教育・研修動画の豊富な制作実績があります。
また、無料相談も承っていますので、ぜひ一度お問い合わせください。

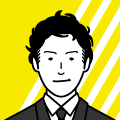

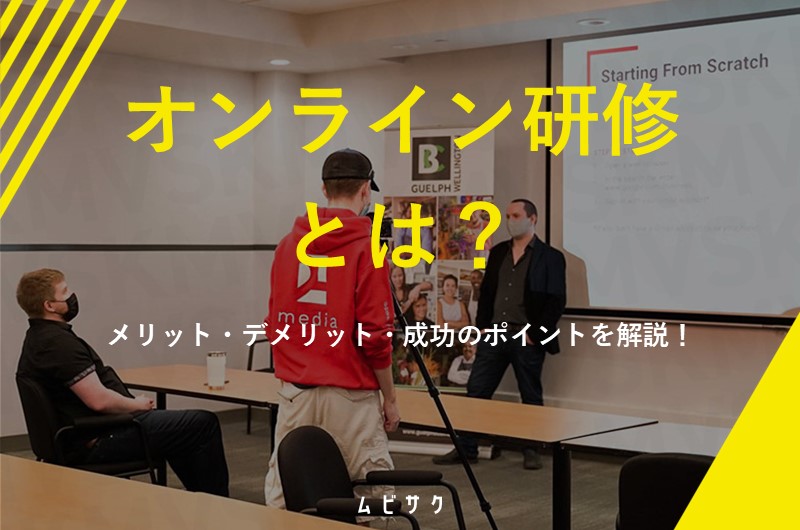
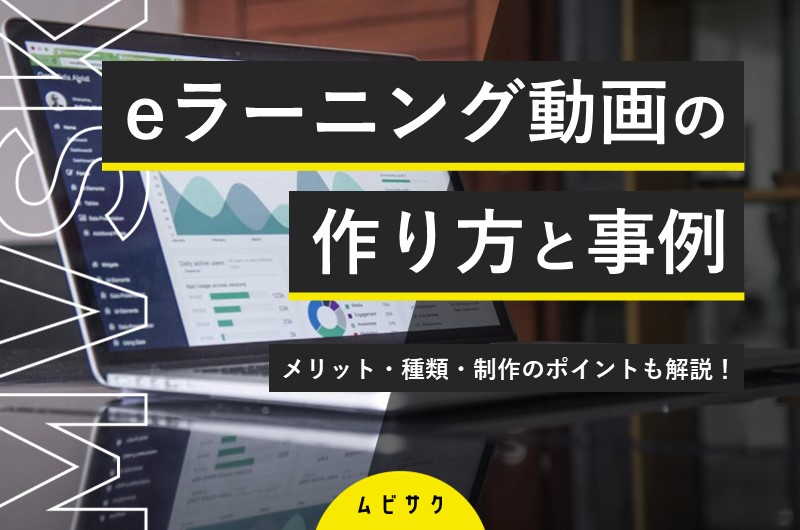
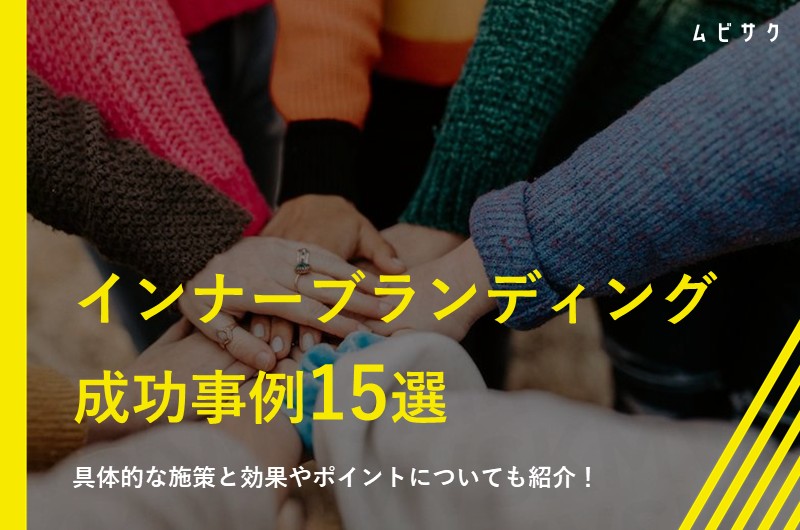

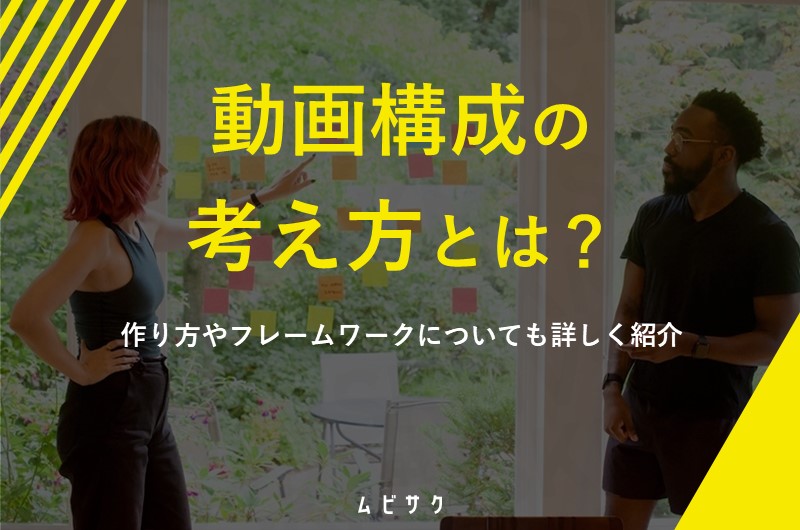


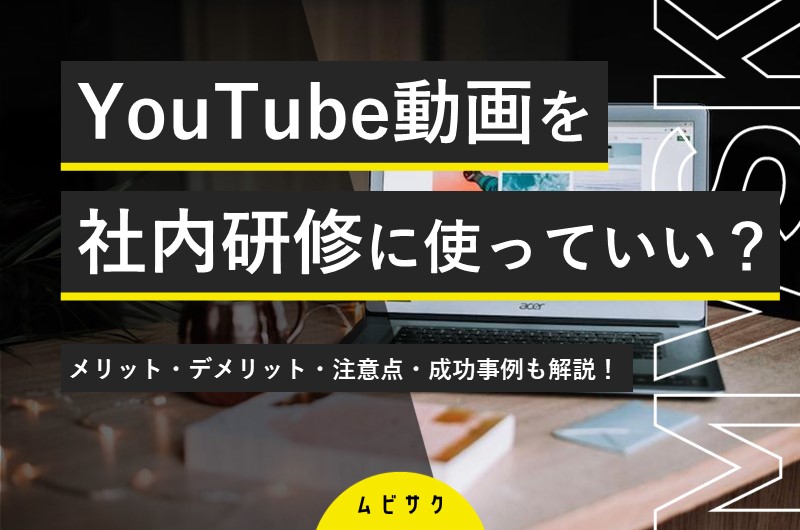

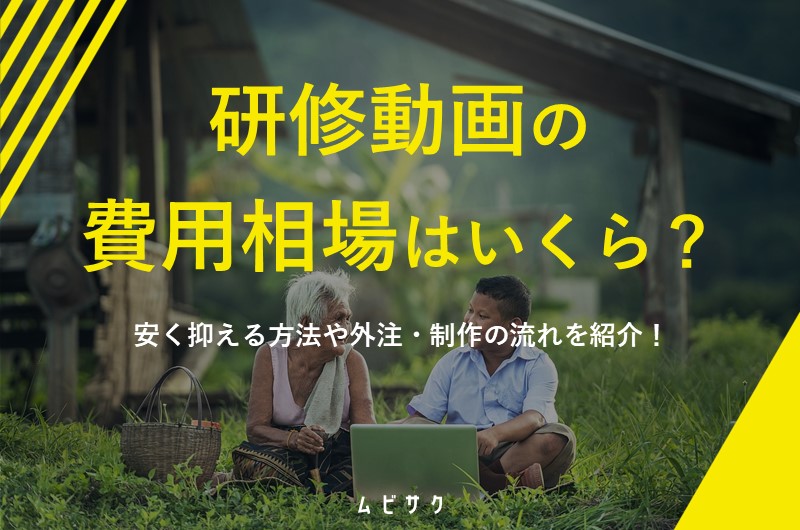
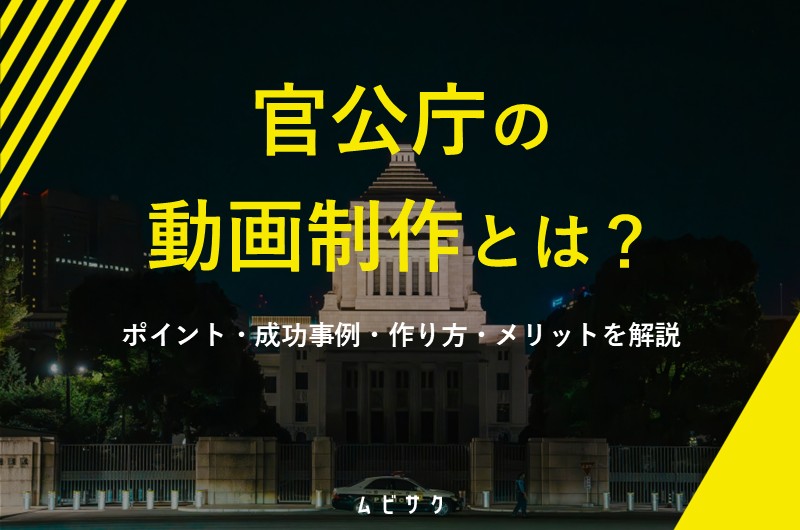
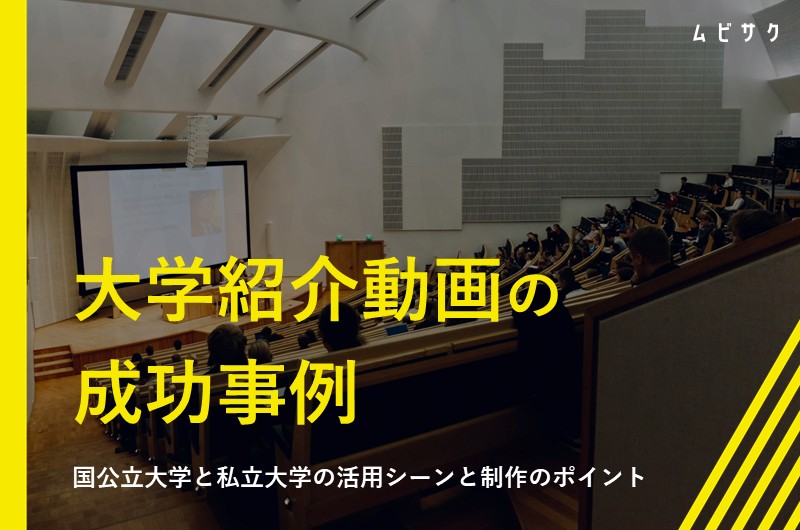

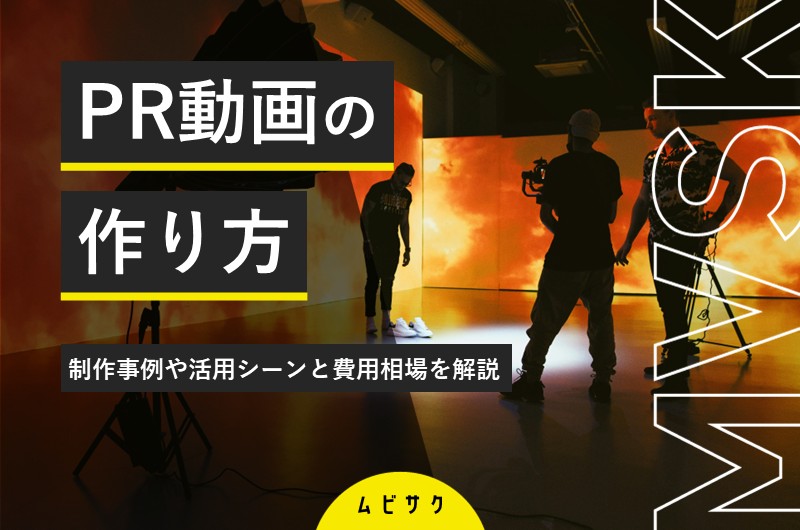

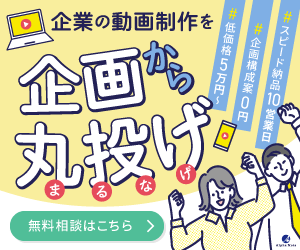


 03-5909-3939
03-5909-3939