動画制作のテーマとは、動画全体の核となる考え方や方向性を指し、企画や構成を決める際の軸となるものです。動画制作を成功させるためには、視聴者に伝えたいメッセージや目的を伝える「テーマ」を明確に定めることが大切です。
本記事では、動画制作のテーマを決める際のポイントを解説します。また、テーマの重要性や考え方、作り方についても、表現方法や目的別にテーマの種類と事例も紹介します。ぜひ、動画制作をする際の参考にしてください。
動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、テーマに沿った動画の豊富な制作実績があります。動画制作を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。
ムビサクの動画制作・映像制作について詳しく知りたい方はこちら
- 動画制作におけるテーマの重要性
- 動画制作のテーマを決める際のポイント
- 動画制作におけるテーマの考え方と作り方
目次
動画制作でこんなお悩みありませんか?
- 動画制作を考えているがどうすればよいかわからない
- 急いで動画を作りたいが方法がわからない
- 高品質な動画を制作したいが自社では難しい…
\ スピーディーに高品質な動画を作るならムビサク /
無料で相談・問い合わせる動画制作のテーマとは?
動画制作のテーマとは、動画全体の軸となる中心的な考え方やメッセージのことを指します。単なるタイトルやジャンルとは異なり、「『誰』に『何』をどう伝えるか?」という目的や方向性を明確にするものです。
例えば、新商品の紹介動画であれば「商品の独自性を印象づける」がテーマになることもあります。テーマが定まっていないと、内容や構成がぶれてしまい、視聴者に伝えたいことがぼやけてしまいます。
一方で、テーマがはっきりしていれば、ストーリー展開や演出方法にも一貫性が生まれ、効果的な動画づくりが可能になります。そのため、制作の初期段階でテーマを固めておくことは、動画の撮影や編集の前における重要な工程といえるでしょう。
動画制作におけるテーマの重要性

動画制作におけるテーマの重要性として、以下のような点があげられます。
- ブレないメッセージを伝えられる
- 視聴者の心に刺さる動画になる
- 企画や構成に迷ったときの判断基準になる
ここでは、それぞれのテーマの重要性について詳しく解説します。
ブレないメッセージを伝えられる
動画制作においてテーマが明確であれば、視聴者に伝えたいメッセージが一貫し、ぶれにくくなります。例えば、採用動画で「企業の成長性と職場の魅力」を伝えることをテーマに定めた場合、インタビューや映像表現の内容も自然とその方向に統一されていきます。一方でテーマがあいまいなままだと、各要素が別々の意図で動き出し、伝えたい情報が分散してしまうこともあります。また、しっかりとテーマを据えておけば、編集段階やクライアントとのやりとりでも迷いが少なくなり、完成度の高い動画に近づけることができます。そのため、メッセージの芯を明確にするうえでも、テーマの設定は重要な役割を果たします。
視聴者の心に刺さる動画になる
視聴者の心に残る動画をつくるには、感情や関心に訴えるテーマを設定することが重要です。例えば、子育て中の家庭向けに制作する動画であれば、「忙しい日常の中での安心感を提供する」といったテーマにすることで、共感を得やすくなります。
テーマが視聴者のニーズや悩みにマッチしていれば、伝えたい情報が自然に届き、行動にもつながる可能性が高まります。一方で、誰に向けた動画かが曖昧だったり、関係の薄いテーマを選んでしまったりすると、見られても心に残らない動画になってしまいます。そのため、視聴者に「自分ごと」として受け取ってもらうためにも、テーマ設計で手を抜かないことが大切です。
企画や構成に迷ったときの判断基準になる
動画制作の過程では、構成や演出方法などに悩む場面が少なくありません。そんなとき、あらかじめ設定したテーマが判断の基準になります。例えば、「新サービスの信頼性を強調する」というテーマであれば、派手な演出よりも実績紹介や顧客の声を取り入れる構成が自然です。
テーマが明確にあることで、方向性のぶれを防ぎ、関係者との意思統一もスムーズに行えます。また、限られた時間や予算のなかで何を優先すべきかを見極める材料にもなります。つまり、企画段階でのブレをなくし、制作全体の効率と質を高めるためにも、テーマはただの飾りではなく、判断軸としての役割を持っているといえるでしょう。
動画制作のテーマを決める際のポイント

動画制作のテーマを決める際には、以下のようなポイントを意識しましょう。
- 「誰」に「何」を伝えるのか明確にする
- 悩みと訴求に一貫性を持たせる
- 1動画1テーマを意識する
- ターゲットの「なぜ」を深堀する
- 視聴者に促したい行動を決めておく
- 動画制作の目的や目標からブレさせない
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
「誰」に「何」を伝えるのか明確にする
動画を制作するうえで最初に明確にすべきなのは、「誰」に向けて「何」を伝えるのかという点です。例えば、新卒向け採用動画であれば、対象は就職活動中の学生であり、伝えるべきは自社の働きがいや成長環境といった魅力になります。ターゲットが曖昧なままでは、訴求すべき内容がぶれてしまい、結果として誰にも響かない動画になる可能性があります。
そのため、視聴者像と伝える内容をセットで具体化しておくことで、構成や演出の方向性も定まりやすく、視聴者の関心に沿った効果的なコンテンツに仕上げることができます。
悩みと訴求に一貫性を持たせる
視聴者に刺さる動画をつくるには、その人が抱える悩みや課題に寄り添う視点が重要です。例えば、業務効率化に関心をもつ企業担当者がターゲットであれば、「作業時間を短縮できる」といった訴求が一貫して伝わる内容にすべきです。
このとき、悩みと訴求の間にずれがあると、視聴者は自分ごととして捉えにくくなります。一貫性が保たれていれば、冒頭の問題提起からラストのアクション促進までが自然につながり、説得力のある動画になります。視聴者の関心を捉えるためには、悩みと解決策のセットで企画を組み立てていくことがポイントです。
1動画1テーマを意識する
限られた動画尺のなかで多くの情報を詰め込みすぎると、結局何を伝えたかったのかがぼやけてしまいます。そこで意識したいのが「1動画1テーマ」です。
例えば、採用動画で「福利厚生」「社員の声」「会社の理念」など複数の要素を詰め込むより、「入社後のキャリアパス」に焦点を絞ることでメッセージが明確になり、印象に残りやすくなります。テーマを一つに絞ることで、構成や演出に無駄がなくなり、視聴者にも伝えたい意図がはっきりと届きます。多くを伝えたい気持ちは理解できますが、まずは一番伝えるべきテーマに集中することが効果的です。
ターゲットの「なぜ」を深堀する
動画を視聴するターゲットが「なぜ」その情報を必要としているのかを考えることで、より刺さるテーマを設定できます。例えば、飲食店のオーナーに向けたサービス紹介であれば、「なぜその機能が必要なのか?」を掘り下げると、忙しい業務の中でもすぐに導入できる利便性やコストの面が重要になるかもしれません。
つまり、ただ表面的な属性やニーズにとどまらず、背景にある動機や課題にまで目を向けることで、動画の内容や語り口がターゲットの心情により近づいていくのです。
視聴者に促したい行動を決めておく
動画の視聴後に視聴者にどんな行動をとってほしいのかを明確にすることで、動画の構成やメッセージが一貫します。例えば、サービス紹介動画で「資料請求してもらう」ことが目的であれば、動画の中でそのメリットを強調したり、最後に具体的なアクションを促す導線を入れたりすることが必要になります。
行動のゴールが曖昧なままでは、印象だけで終わってしまい、期待した成果につながらないこともあります。あらかじめ「お問い合わせ」「お申し込み」「シェア」「コメント」など、促したい行動を一つに絞っておけば、視聴者の関心を逃さず、動画の効果を高めることができます。
動画制作の目的や目標からブレさせない
制作の過程では、さまざまなアイデアや意見が出てくることがありますが、動画の目的や目標を軸にブレない判断を下すことが重要です。例えば、ブランディング目的の動画なのに、売上を直接促すような構成に傾いてしまうと、本来の狙いから外れてしまいます。
目的が「企業イメージの向上」であれば、内容やトーンもそれに合ったものに統一されるべきです。制作の初期に設定した目的やKPIを常に意識しておくことで、途中の迷いや方向転換にも冷静に対応できるでしょう。
【表現方法別】動画制作のテーマの種類と事例
動画制作のテーマの種類は、表現方法ごとに以下のように分けられます。
- アニメーション動画
- 実写動画
- 3DCG動画
ここでは、それぞれのテーマにおけるメリットや特徴を事例とともに解説します。ぜひ、動画制作を始める際の参考にしてください。
アニメーション動画
事例:YouTubeチャンネル掲載用の教育・講座動画
アニメーション動画は、抽象的な内容や複雑な情報をわかりやすく伝えたい場面で活用されます。例えば、ITサービスの仕組みを紹介する場合、実際の映像では伝わりにくい処理の流れや画面遷移を、図解やキャラクターを使って視覚的に表現することで、理解を助けることができます。
アニメーションならではの柔軟な表現により、ストーリー性やテンポ感も自在にコントロールできるため、視聴者を飽きさせずに最後まで見てもらいやすくなります。また、撮影の手間がないため、限られた予算やスケジュールでも制作しやすいという特徴もあります。そのため、サービス紹介から教育・研修まで幅広いシーンで効果的に使われています。
実写動画
事例:クラウドファンディング向け商品説明動画
実写動画は、リアリティや感情の伝達を重視したいときに適しています。例えば、インタビューや製品の使用シーンを映すことで、企業の雰囲気や実際のサービス体験を視聴者に具体的に伝えることができます。登場人物の表情や声色、背景の空気感など、細かいニュアンスを直接感じ取れるため、共感や信頼感を得やすいのが特徴です。
また、実在の人物や場所を用いることで、視聴者に対する説得力も高まります。ただし、撮影場所の確保や天候の影響、出演者の手配など、制作における調整事項が多くなるため、スケジュール管理や事前準備がポイントとなります。商品プロモーションや採用動画、会社紹介などでよく利用されています。
3DCG動画
事例:製造業における3DCG動画
3DCG動画は、工業製品や機械構造など、実物だけでは伝わりにくい技術的な内容を視覚的にわかりやすく表現できる手法です。例えば、製造装置の内部構造や作動の流れを紹介したい場合、3DCGなら実際に分解して見せることができ、製品の特長や強みを具体的に伝えられます。
動作のシミュレーションや拡大図、断面表示といった演出も可能で、営業資料や展示会での説明にも効果的です。また、完成前の設計段階でも、3DCGを活用すれば実機がなくても訴求力のある映像を制作できます。産業機器や部品メーカーのPRに向いた手法といえるでしょう。
【目的・用途別】動画制作のテーマの種類と事例
動画制作のテーマの種類は、目的・用途ごとに以下のように分けられます。
- ブランディング動画
- 認知拡大動画
- リード獲得動画
- カスタマーサポート・ハウツー動画
- 研修・マニュアル動画
- 採用動画
- 社会貢献・SDGs動画
ここでは、それぞれの動画制作のテーマについて事例を交えて解説します。
ブランディング動画
事例:絵本「ちっちゃな おさかなちゃん」YouTubeプロモーション動画
ブランディング動画は、企業や商品の世界観、価値観、信念といった目に見えない「ブランドの核」を伝えます。例えば、込められた想いや大切にしていることを映像で表現することで、視聴者にブランドへの共感や信頼を育むことができます。
直接的な商品の売上につなげるというよりも、中長期的な関係づくりやイメージ形成を目的として制作されることが多く、企業のファンを増やしたい場面などに向いています。映像のトーンや音楽、ナレーションの使い方など、細部にまでブランドらしさを宿すことで、視聴者の記憶に残る動画となります。
認知拡大動画
事例:SalesforceのAI入力ツールの広告動画
認知拡大動画は、自社の商品やサービスの存在をまだ知らない人に広く知ってもらうことを目的としています。例えば、新規に開発したアプリを多くのユーザーに届けたい場合、使い方の一部や魅力的な特徴を短い時間で印象づける構成が効果的です。
SNS広告やYouTube動画として活用されるケースが多く、視聴者の興味を引く導入や、見終わったあとに記憶に残るメッセージが求められます。また、視覚的なインパクトやストーリー性を持たせることで、シェアや拡散の可能性も高まります。
リード獲得動画
事例:YouTube広告用アニメーション
リード獲得動画は、見込み顧客の関心を引き出し、次のアクションにつなげることを目的としています。例えば、BtoB向けのサービスであれば、課題の提示からソリューションの紹介、導入メリットまでをコンパクトにまとめた動画を通じて、資料請求やお問い合わせを促す構成が考えられます。
視聴者に「自分のことだ」と感じさせる課題提起と、具体的な解決手段を示す内容が重要となり、信頼性を高めるために導入事例や数値実績などを盛り込むこともあります。営業活動の前段階で接点を持つ手段として、ターゲットを意識したストーリー設計が求められます。
カスタマーサポート・ハウツー動画
事例:パートナー向けインストラクション動画
カスタマーサポート・ハウツー動画は、商品やサービスの使い方、トラブル対処法などを視覚的に案内することで、ユーザーの不安や疑問を解消する役割を担います。例えば、複雑な設定が必要な機器であれば、操作手順をひとつずつ見せる動画を用意することで、文字マニュアルでは伝わりにくい細かなポイントまで丁寧に説明できます。
視聴者が自分のペースで確認できるため、サポート窓口への問い合わせ件数の軽減にもつながり、ユーザー満足度の向上にも貢献します。トラブル時だけでなく、初期設定や便利機能の紹介などにも活用され、長期的な顧客サポートの一環として効果的です。
研修・マニュアル動画
事例:施設の利用方法の解説動画
研修・マニュアル動画は、業務知識や作業手順を効率よく伝える手段として活用されます。例えば、接客対応や安全管理など現場での行動が重要な業種では、言葉や文字だけでは伝わりにくい動作や判断を映像で示すことで、より具体的に理解してもらうことができます。
口頭での説明では個人差が出やすい内容も、動画を用いれば一定の品質で繰り返し教育できるため、新人教育や多店舗展開時の研修にも効果的です。また、記録として残すことでナレッジの共有にもつながります。
採用動画
事例:施設警備職の求人募集動画
採用動画は、求職者に対して企業の雰囲気や働く魅力を伝えることで、応募のきっかけをつくる役割を果たします。例えば、働く社員の仕事内容を紹介することで、入社後の具体的なイメージが湧きやすくなり、企業選びの判断材料にもなります。
文字や写真では伝えきれない社内の空気感や人間関係などを、映像なら自然なかたちで伝えることができ、ミスマッチの防止にもつながります。新卒・中途採用どちらにも対応でき、会社説明会の代替や補足資料としてもおすすめです。
社会貢献・SDGs動画
事例:カーボンニュートラルとSDGsの取り組み動画
社会貢献やSDGsに関する動画は、企業が持つ社会的な視点や取り組みを伝え、共感や信頼を形成するために使われます。例えば、エコな製品づくりの紹介やリサイクル促進の取り組みなどを映像で紹介することで、企業の姿勢をわかりやすく伝えることができます。
社会貢献・SDGs動画は商品やサービスの宣伝とは異なり、企業の価値観や社会との関わり方を表現することが目的であり、長期的なブランド形成やCSR活動の報告にもつながります。また、社内向けに共有することで、社員の意識づけやインナーブランディングにもおすすめです。
なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、アニメーション動画から実写動画、3DCG動画まで、テーマにあわせた豊富な動画制作の実績があります。
無料相談も承っております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
動画制作におけるテーマの考え方と作り方
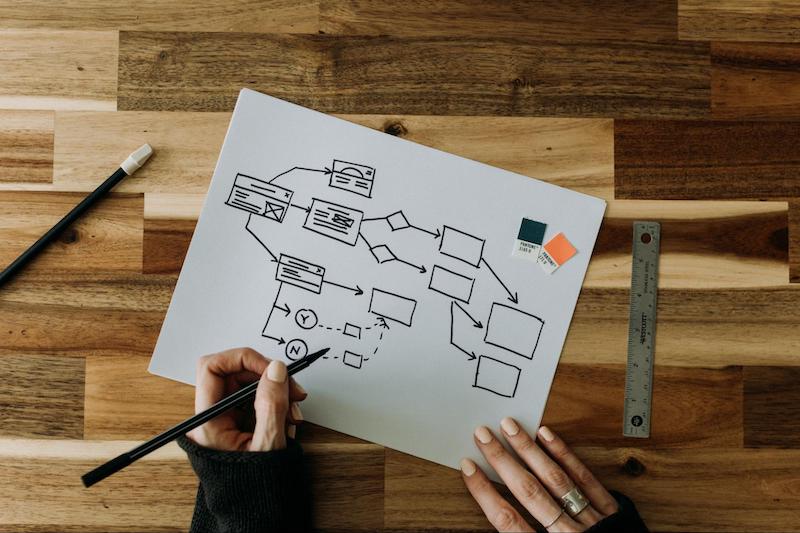
動画制作におけるテーマの考え方と作り方は、以下の手順で進みます。
- step1:動画の目的を明確にする
- step2:視聴者のターゲット像を考える
- step3:配信する媒体を選定する
- step4:テーマに合わせて動画の企画や構成を作成する
ここでは、それぞれの進め方について詳しく解説します。
step1:動画の目的を明確にする
動画制作のテーマ決めでの第一歩は、「何のためにその動画をつくるのか?」を明確にすることです。例えば、新商品を紹介する動画であれば、視聴者に購入を促すのか、ブランドの存在を知ってもらうのかで、表現の仕方や構成が大きく変わってきます。
目的が曖昧なままでは、伝えるべき内容が定まらず、結果として印象に残りにくい動画になる可能性があります。一方で、目的がはっきりしていれば、どんな要素を取り入れるべきか、どういったゴールを目指すべきかが見えてきます。動画の成果を判断するうえでも、テーマ決めの最初に目的を具体的に言語化しておくことは欠かせない準備と言えるでしょう。
なお、目的を決める際には企画書のテンプレートを活用することもおすすめです。以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
step2:視聴者のターゲット像を考える
動画のテーマを決めるには「誰に見てもらうのか?」を明確にし、人物像に合わせた内容設計を行うことが大切です。例えば、ビジネスシーンでのBtoB動画であれば、論理的な構成や実績データが重視されますが、学生向けの採用動画であれば、働く人の姿や社内の雰囲気を映す方が共感を得やすくなります。
年齢や職業、価値観、情報リテラシーなど、視聴者の背景によって、動画のテーマや響く言葉、映像のトーンは異なります。ターゲット像を詳細に描き出すことで、動画全体の方向性が明確になり、結果的に自分ごと化しやすくなるでしょう。
なお、ターゲット像に合わせたシナリオづくりについては、以下の記事も参考にしてください。
step3:配信する媒体を選定する
動画のテーマは配信する媒体によっても異なります。動画の内容や構成を決めるうえでは、「どこで視聴されるか?」という配信媒体の特性を踏まえることも欠かせません。例えば、InstagramやTikTokで拡散したい動画であればショート動画でテンポよく展開し、冒頭に視聴者の関心を引く要素を入れる工夫が必要です。
一方、会社のWEBサイト内で掲載する動画であれば、機能やメリット、解決できる課題についてまとめておくとよいでしょう。媒体ごとにユーザーの視聴環境やモチベーションが異なるため、媒体に合った動画のテーマや長さ、内容を選ぶことが成果につながります。
なお、動画配信におすすめのSNS媒体については、こちらの記事でもまとめています。
step4:テーマに合わせて動画の企画や構成を作成する
目的とターゲット像、配信媒体が固まったら動画制作のテーマはほぼ完成です。動画制作に映る前の最後のステップとして、考えたテーマに合わせて企画や構成を作成していきましょう。
企画や構成づくりで重要な点は、内容に無駄をつくらず、伝えたいテーマをぶらさないことです。長すぎる説明や脈絡のない演出は視聴離脱の原因になります。限られた時間の中で、どの順番で何を伝えるかを緻密に設計することが、メッセージを的確に届けるためのポイントです。そのため、完成度の高い動画は、構成の段階でほぼ方向性が決まっているとも言えます。
また、動画構成の考え方についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、アニメーション動画から実写動画、3DCG動画まで、テーマにあわせた豊富な動画制作の実績があります。
無料相談も承っております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
動画制作のテーマに関するよくあるご質問
動画制作のテーマについてのご質問はかなり多くいただきます。その中から、頻度の高いものへの回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
動画のテーマとは何ですか?
- 動画のテーマとは、動画全体を貫く「中心的なメッセージ」や「伝えたい考え方」のことです。単なるタイトルやジャンルとは異なり、「誰に向けて、何を伝えるのか?」という目的や方向性を明確にする役割があります。テーマが明確であれば、ストーリーや演出の軸がぶれず、視聴者にとっても理解しやすい動画になります。
動画制作のテーマはどのように決めますか?
- 動画のテーマを決める際は、まず「動画の目的」をはっきりさせることが重要です。次に、「誰に見てもらいたいか」というターゲット像を明確にします。そのうえで、配信する媒体(YouTube、SNS、WEBサイトなど)に応じた尺や表現方法を検討します。最後に、テーマに沿って動画の企画や構成を練り上げていきます。
動画のテーマおけるおすすめは何ですか?
- 動画のテーマは目的に応じて選ぶことが重要ですが、初めて制作する場合や迷ったときには「認知拡大動画」や「リード獲得動画」がおすすめです。自社の魅力をわかりやすく伝える動画や、お問い合わせなどのリード獲得動画は売上に直結しやすいです。そのため、日々の営業活動のなかで得た情報からテーマづくりが可能です。
まとめ

動画制作のテーマとは、動画全体の軸となる中心的な考え方やメッセージのことを指します。単なるタイトルやジャンルとは異なり、「『誰』に『何』をどう伝えるか?」という目的や方向性を明確にするものです。
テーマを決めて動画制作を進めることで、ブレないメッセージを伝えられ、視聴者の心に刺さる動画になります。また、プロジェクトチームのなかで、企画や構成に迷ったときの判断基準になる点からも重要視されています。
なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、アニメーション動画から実写動画、3DCG動画まで、テーマにあわせた豊富な動画制作の実績があります。
無料相談も承っております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

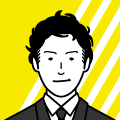
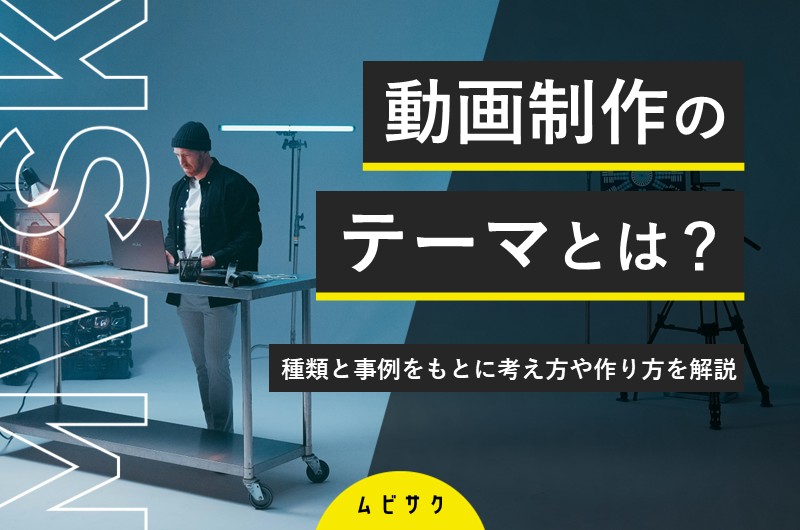

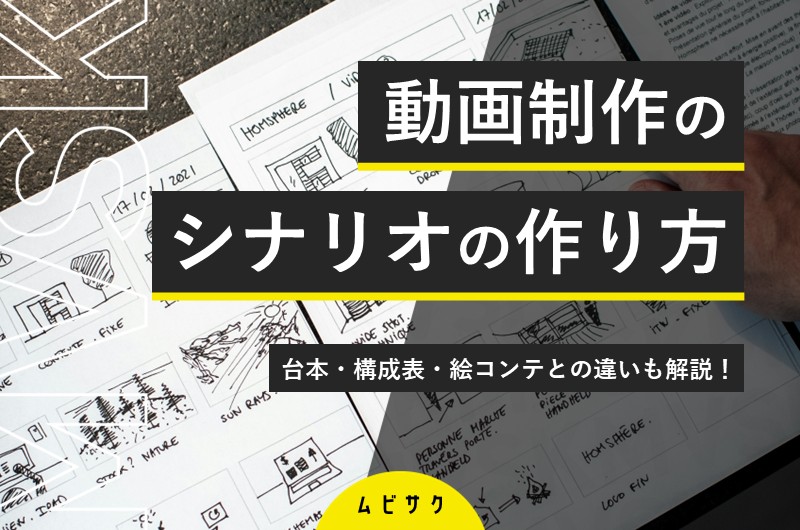

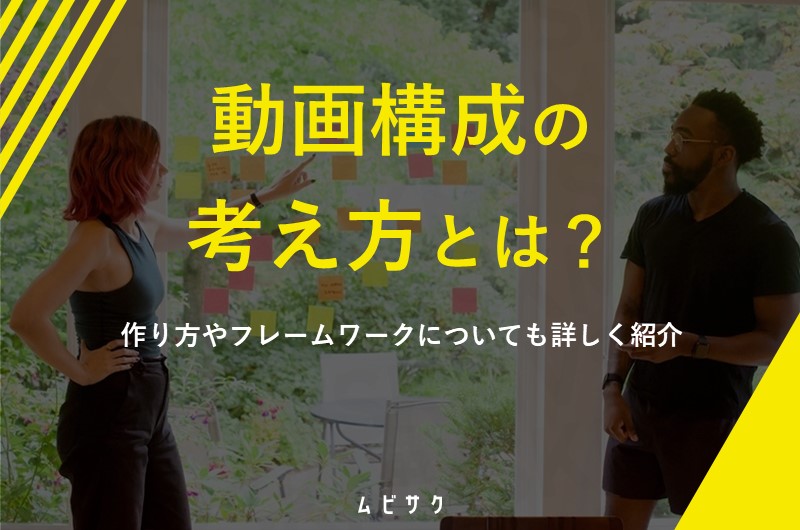

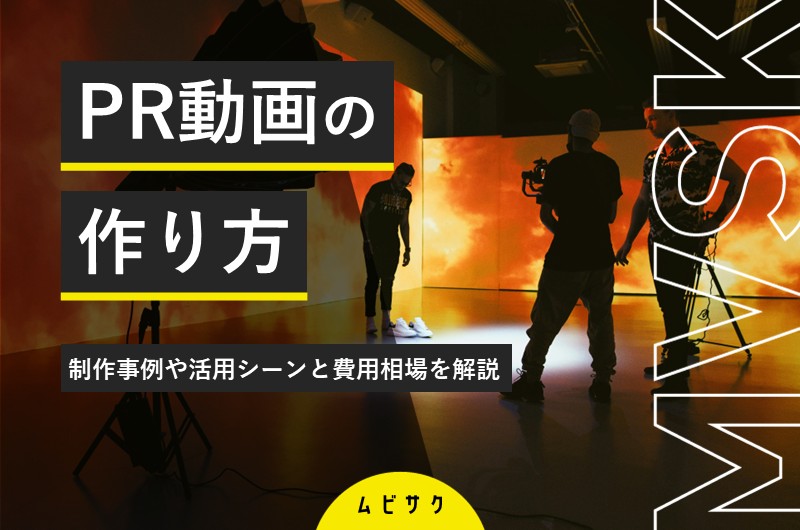

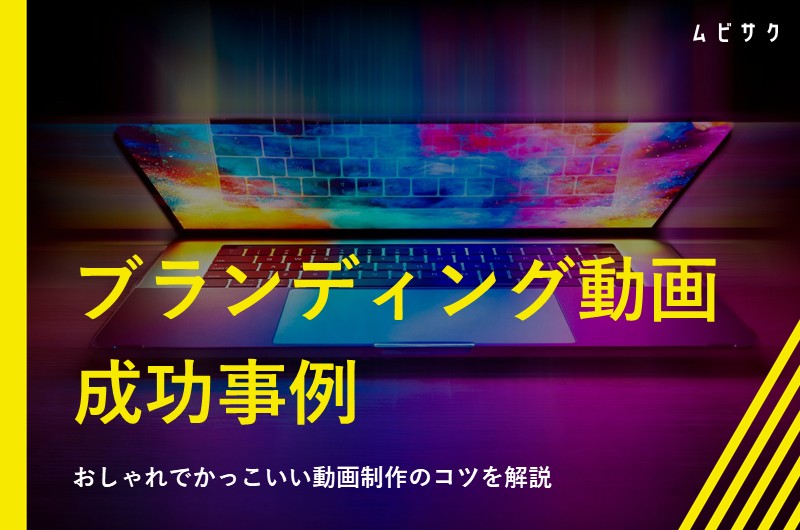
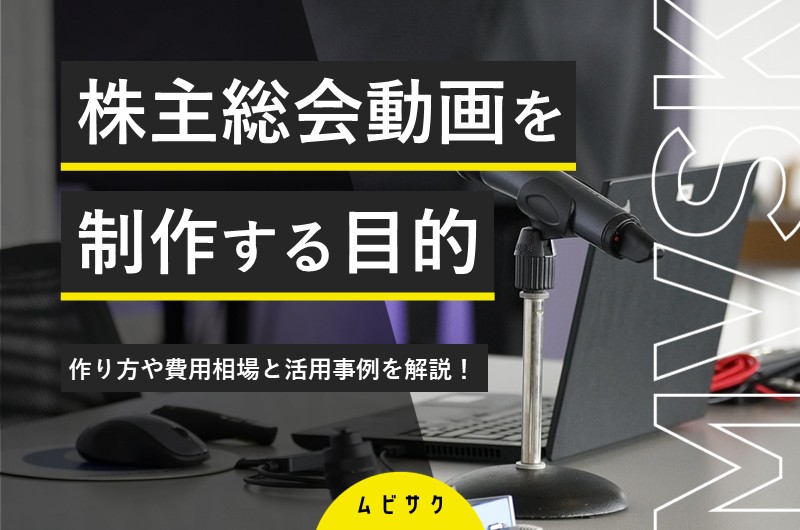
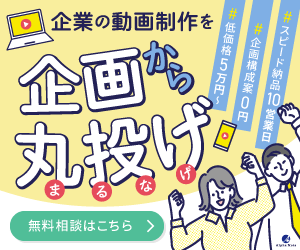

 03-5909-3939
03-5909-3939