地方自治体の情報発信において、近年注目されているのがVR(仮想現実)や360度動画の活用です。まるでその場にいるかのような臨場感を提供できるこれらの技術は、観光プロモーションや移住促進、防災訓練、地域文化の発信など、さまざまな用途で導入が進んでいます。
本記事では、自治体がVRや360度動画を活用するメリットや具体的な活用シーン、実際の活用事例を紹介します。VR動画を制作する際のポイントについても解説しますので、地域振興や住民サービスの向上の参考にしてください。
動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、自治体PR動画の豊富な制作実績があります。動画制作を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。
ムビサクの自治体PR動画の制作について詳しく知りたい方はこちら
- 自治体がVR・360度動画を制作するメリット
- 自治体がVR・360度動画を制作する際のポイント
- 自治体におけるVR・360度動画の活用事例
目次
動画制作でこんなお悩みありませんか?
- 動画制作を考えているがどうすればよいかわからない
- 急いで動画を作りたいが方法がわからない
- 高品質な動画を制作したいが自社では難しい…
\ スピーディーに高品質な動画を作るならムビサク /
無料で相談・問い合わせるVRとは?
VR(バーチャル・リアリティ)とは、仮想空間をあたかも現実のように体験できる技術のことを指します。専用のゴーグルやヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着することで、視覚や聴覚に働きかけ、実際には存在しない空間の中を自由に移動したり、物に触れたりするような感覚を得られます。
例えば、観光地の風景を360度で再現することで、現地に行かずともその場の雰囲気を味わえる仕組みが実現します。教育、医療、建築など多分野で導入が進むなか、自治体においても住民サービスや地域活性化を目的とした活用が広がりつつあります。
なお、VRについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
自治体がVRを活用するメリット

自治体がVRを活用するメリットとして、以下のような点があげられます。
- 観光地や名所を360度で体験できる
- 移住希望者に街の雰囲気をリアルに伝えられる
- 研修や学びのコンテンツとしても応用できる
ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
観光地や名所を360度で体験できる
VRを活用することで、観光地や名所の魅力を360度の視点でリアルに伝えることが可能になります。例えば、季節ごとに表情を変える自然風景や、歴史的建造物の内部など、通常は訪問が難しい場所も臨場感をもって紹介できます。
ユーザーは視点を自由に動かしながら映像を体験できるため、一方向からの説明では伝わりにくい空間の奥行きや雰囲気も感じ取れます。さらに、時間や場所を選ばずに体験できるため、観光のきっかけづくりや来訪意欲の喚起にもつながります。その結果、現地を訪れる前に期待感を高めることができ、観光プロモーションとしての効果が期待されます。
移住希望者に街の雰囲気をリアルに伝えられる
移住を検討する人にとって、住環境の雰囲気や利便性は大切な判断材料です。VRを活用すれば、街並みや周辺施設、公共交通機関の様子などを360度の映像で体感でき、実際にその場を歩いているかのような感覚で地域の特徴を把握できます。
例えば、子育て世代向けに学校や公園、商業施設を紹介する映像を用意することで、暮らしのイメージがしやすくなるでしょう。また、遠方に住む移住希望者にも時間や距離の制約なく地域を体験してもらえるため、移住相談や地域紹介イベントなどでの活用も効果的です。
研修や学びのコンテンツとしても応用できる
VRの特性を活かすことで、自治体職員や住民向けの研修や教育コンテンツにも応用することが可能です。例えば、防災訓練で災害発生時の状況を仮想的に再現し、避難経路や対応手順を体験的に学ぶといった活用方法があります。
文字や写真だけでは伝えきれない緊迫感や判断の難しさを、VRであればリアルに伝えることができます。また、地域資源や文化について学ぶ体験型教材としても効果的で、視覚的な理解を深めやすい点がメリットです。加えて、複雑な業務の流れや機器の操作手順を反復して学べる環境としても機能し、職員のスキルアップや住民の学習機会の充実にもつながります。
自治体におけるVRの活用シーン

自治体におけるVRの活用シーンとして、主にいかのような場面があります。
- 観光プロモーション
- 移住・定住促進
- 地域文化・伝統・テクノロジーの発信
- 防災訓練や研修資料
- 都市計画の可視化
ここでは、それぞれの活用シーンについて詳しく解説します。
観光プロモーション
観光分野においてVRは、地域の魅力を臨場感ある形で伝える手段として活用されています。例えば、名所の四季折々の風景や祭りの様子を360度の映像で紹介することで、現地に足を運ばずとも空気感や雰囲気を体感できます。
視点を自由に動かせるVRならではの没入感が旅行者の興味を引き、訪問意欲を高めるきっかけとなります。また、パンフレットやウェブサイトでは伝えきれない情報を補完できるため、海外からの観光客に向けたプロモーションにも適しています。自治体が地域資源を効果的に伝えるための手法として、イベント会場や交通機関の待合スペースなどでの上映が進められています。
なお、観光プロモーション動画の成功事例はこちらでも紹介しています。
移住・定住促進
移住や定住を検討する人々にとって、その地域での生活がどのようなものかを具体的にイメージできるかどうかは大きな判断材料になります。VRを用いることで、駅周辺や住宅地の様子、商業施設、医療機関、教育施設などをリアルに体験することができます。
例えば、子育て支援が充実した地域では、保育園や子育て広場の雰囲気を360度動画で紹介することで、安心感を伝えることができます。現地に足を運ぶことが難しい遠方在住者にも地域の特色を届けられるため、オンラインでの移住相談や説明会と組み合わせた活用も効果的です。
なお、自治体での動画活用については、こちらの記事も参考にしてください。
地域文化・伝統・テクノロジーの発信
地域ごとに息づく文化や伝統、そしてそれを支える技術の魅力を発信する手段としても、VRは活用されています。例えば、伝統工芸の職人技や地域祭りの準備風景など、現地でしか見られない貴重な場面を記録し、360度動画として残すことで、来訪者だけでなく地域住民にも新たな気づきをもたらしてくれるでしょう。
また、最先端の技術や産業を持つ地域であれば、企業や研究施設の紹介にVRを用いることで、地域の先進性を視覚的にアピールすることも可能です。
なお、インバウンド動画として海外への情報発信も増えてきています。インバウンド動画についての詳細はこちらも参考にしてください。
防災訓練や研修資料
災害時の初動対応や避難行動を訓練する際、VRは現実に近いシミュレーション体験を可能にします。例えば、地震発生直後の建物内の様子や避難経路を再現したVR映像を用いることで、視覚的に危険性や行動の選択肢を学ぶことができます。
文章や図解だけでは理解が難しい状況を立体的に示せるため、住民向けの防災講習や職員の研修資料として導入される事例が増えています。加えて、災害以外の分野でも、交通安全、福祉、医療などの研修用途として活用が広がっており、視覚と体験を通じて理解を深める教育手法として定着しつつあります。
都市計画の可視化
都市開発や再整備における住民理解の促進にも、VRは有効な手段となっています。例えば、新しく整備される駅前広場や公共施設の完成予想図を360度動画で提示することで、図面や模型だけでは伝えきれない空間の広がりや動線のイメージを視覚的に共有できます。
住民説明会などでは、実際にその場に立っているような感覚で新しい街の姿を体験できるため、意見交換も活発になりやすくなります。また、バリアフリー化や緑地整備の計画も視覚的に理解しやすくなるため、多様な立場の人々の声を反映した合意形成にもつながります。
自治体がVR動画を制作する際のポイント

自治体がVR動画を制作する際のポイントとして、以下のような点を意識しましょう。
- 目的やターゲットを明確にしておく
- 「体験」を重視した没入感を与える
- 撮影・編集は専門家に依頼する
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
目的やターゲットを明確にしておく
自治体がVR動画を制作する際には、目的とターゲットを明確にすることがポイントです。例えば、観光客に向けたプロモーションであれば、映像の中で伝えるべき情報や演出は観光資源の魅力に集中させる必要があります。
一方で、移住希望者を対象とする場合には、生活環境や子育て支援、アクセス情報など実生活に直結する内容を盛り込むことが求められます。あらかじめ情報発信の狙いや対象層の関心を整理しておくことで、映像の内容や構成に一貫性を持たせ、効果的な訴求につなげることができます。
「体験」を重視した没入感を与える
VR動画の特性は、映像の中に「入ったような」体験ができることにあります。自治体がこの技術を活用する際には、単なる映像紹介にとどまらず、見る人が実際にその場を訪れているように感じられる没入感の演出を意識することがポイントです。
例えば、視聴者の目線の高さに合わせて撮影したり、360度カメラを使って周囲の風景を自然に見渡せるようにしたりすることで、現地にいるかのようなリアリティを生み出せます。体験的な映像構成を心がけることで、印象に残るコンテンツとなり、情報の受け取り方にも違いが出てきます。
撮影・編集は専門家に依頼する
VR動画の制作には特殊な機材や高度な編集技術が求められるため、撮影や編集の工程は専門家に依頼するのが現実的です。例えば、360度カメラによる撮影ではカメラの設置位置や光の調整が没入感につながり、編集時には視点の移動に配慮する必要があります。
動画制作のプロに依頼することで、技術面だけでなく、構成や演出の相談にも乗ってもらえるため、映像の完成度を高めることができます。限られた予算内でも、品質を担保するために、動画制作会社への依頼を検討しましょう。
なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、自治体向け動画における豊富な制作実績があります。
無料相談も承っております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
自治体におけるVRの活用事例
自治体におけるVRの活用事例として、以下の自治体を紹介します。
- 静岡県富士宮市
- 東京都
- 福島県
- 和歌山県田辺市
- 愛知県津島市
- 長野県諏訪郡富士見町
- 富山県高岡市
- 大阪府摂津市
- 埼玉県草加市
- 大分県佐伯市
- 埼玉県北足立郡伊奈町
- 山口県岩国市
- 石川県羽咋市
- 大阪府大阪市中央区
- 長野県上伊那郡箕輪町
- 茨城県稲敷郡阿見町
- 鹿児島県
- 大阪府羽曳野市
なお、ここで紹介する動画は弊社で制作されたものではありませんが、ぜひ活用の参考にしてください。
静岡県富士宮市
引用:【公式】富士宮360°VR Fujinomiya The gateway to Mt. Fuji 4K – 静岡県富士宮市 Fujinomiya City, Shizuoka, Japan
静岡県富士宮市では、VR動画を活用しています。富士山の南西麓に広がる自然豊かな街で、富士山本宮浅間大社の門前町として歴史と信仰が息づいています。
動画では、富士山観光の玄関口である富士山本宮浅間大社の鳥居をくぐり抜けるシーンから始まる壮大さがポイントです。豊かな湧水がもたらす美しい自然景観から美味しい食材、アウトドアアクティビティなどをVRで体験できます。
東京都
引用:360°映像!VR 東京水ができるまで
東京都の水道施設を紹介する360度動画です。東京の水道水がダムからどのように家庭に届くかをわかりやすく解説しています。
動画では、キャラクターを用いたわかりやすい表現になっている点がポイントです。普段では見学できないシーンを臨場感あふれる映像で疑似体験できる点がVRのメリットといえるでしょう。
福島県
引用:福島の建設業役割 360度ビュー
福島県では、「ふくけんビルド」として福島県の建設業の魅力を発信するポータルサイトを運営しています。360度動画として重機の操縦を体感できる映像を配信しています。
実際に重機を操縦しているかのような臨場感あふれる映像がポイントです。また、雪国での除雪作業はなかなか見学しづらいシーンですが、VRのおかげで安全に見学できます。
和歌山県田辺市
和歌山県田辺市は、南西紀伊半島に広がる自然豊かな中核都市で、森林や渓谷、海岸と温泉地が点在します。歴史的には「熊野古道」の中辺路や大辺路が交差し、歴史と文化が調査された街づくりが特徴です。
動画では、「バーチャルたなべプロジェクト」の一環として制作されています。少子高齢化や人口減少、災害への備えなど、さまざまな課題への新しい取り組みとして、VR動画で田辺市を体験することができます。熊野古道の観光体験や災害時の避難ルートの事前確認などが動画でできる点がポイントです。
愛知県津島市

愛知県津島市には、風情・情緒あふれ、魅力ある景観が多くあります。毎年7月に開催される「尾張津島天王祭」は600年近く続いており、この車楽舟行事はユネスコ無形文化遺産にも登録されています。
津島市では、VR技術を活用して景観についてのワークショップを実施しました。VR上で将来イメージを共有し、町並みを守るルールを考えるきかっけになっています。
長野県諏訪郡富士見町
引用:長野県諏訪郡富士見町「【360度動画】入笠山トレッキング ~360度の大パノラマ ~(夏)」
長野県諏訪郡富士見町は、高原地帯に位置し、東に八ヶ岳、西に南アルプス、南に富士山を望む絶景のロケーションが魅力です。春から秋はトレッキングや花畑、冬は雪景色や高原リゾートが楽しめる自然と文化が調和する町です。
VR動画では、入笠山を紹介して、高山植物を360度で体験できます。日本三百名山にも数えられる南アルプス北端の山で、ゴンドラリフトにより山頂へ簡単にアクセスできるトレッキングスポットとして有名です。
富山県高岡市
富山県高岡市は富山県北西部、日本海に面し、富山市に次ぐ県内第2の都市です。1609年に加賀藩主・前田利長が高岡城を築き城下町として発展しました。その後は、高岡銅器や漆器などの伝統工芸と、アルミや化学工業などの近代ものづくり産業が融合し発展を続けています。
動画では、江戸時代の加賀藩において藩主が参勤交代や鷹狩りの際に休憩した高岡御旅屋の魅力を伝えています。イラストやアニメーションも交えた映像であり、当時の様子をイメージしやすくなっています。
大阪府摂津市
引用:大阪府摂津市「千里丘駅西地区の再開発を覗いてみよう!-VR動画」
大阪府摂津市は大阪の北部に位置し、淀川沿いに広がる平坦地と自然に育まれた環境が特徴で、JR・阪急・大阪モノレールが通り、大阪駅や京都駅への通勤アクセスも良好です。事業所が数多く立地する「産業のまち」であり、教育や子育て支援も充実しています。
VR動画として、市の再開発事業を紹介しています。JR千里丘駅西地区は、駅前に旧来の木造住宅や狭い道路が密集し、交通渋滞や土地利用の課題を抱えていました。課題を解消し、にぎわいある駅前拠点を形成するため、都市機能の充実と災害に強い住環境の形成や、交通機能の強化を目指す再開発事業をわかりすく動画で表現しています。
埼玉県草加市
引用:埼玉県草加市「【360°VR動画】 第38回草加市美術展 <VR美術展>」
草加市は埼玉県の東南部に位置し、東京都足立区に隣接しています。江戸時代、日光街道の宿場町「草加宿」として栄え、松尾芭蕉の「おくのほそ道」にも登場します。綾瀬川や草加松原の松並木が美しく、草加せんべいや皮革製品、本染め浴衣など伝統産業も盛んな、歴史と文化が調和した街です。
360度動画では、草加市美術展の様子を紹介しています。市内在住・在勤・在学及び市内の公共施設を活動拠点としている方々から公募した日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の6部門の作品が展示されます。展示の様子を360度VR動画としてオンラインでも配信し、自宅からでもアートを鑑賞できる取り組みがされました。
大分県佐伯市
大分県佐伯市は、大分県の南東端に位置します。江戸時代には佐伯藩の城下町として栄え、「佐伯の殿様、浦でもつ」と称されるほど海の幸や山の幸に恵まれています。リアス式海岸や清流、原生林が広がり、国定公園やユネスコエコパーク指定地域がある豊かな自然に恵まれた地域です。
動画では、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークエリアの佐伯市宇目にある景勝地「藤河内渓谷」を360度見渡すことができます。透明度の高い水と巨大な花崗岩の一枚岩に形成された無数の甌穴(おうけつ)群が美しく連なる様子が映像にまとめられており、つい足を運びたくなるでしょう。
埼玉県北足立郡伊奈町
引用:埼玉県北足立郡伊奈町「イナ王国と秘密のローズガーデン」
埼玉県伊奈町は埼玉県北足立郡に位置し、東京都心から近いベッドタウンでもあります。江戸時代、伊奈備前守忠次が治水・新田開発を進めた地域で、町名はその功績に由来しています。また、バラを町の花とする「バラのまち」としても知られています。
伊奈町と宝探しコンテンツ制作会社が連携したVR動画を配信しています。町内を舞台に、「イナ王国」の王家のティアラやバラが消えたというストーリーをもとに、参加者はスマホを使って宝の地図を頼りに謎解きやVR動画視聴などを体験できます。町のバラ園や文化資源を活かした観光振興イベントとして注目を集めました。
山口県岩国市
引用:山口県岩国市「シティプロモーション用360°VR動画」
岩国市は山口県東部、瀬戸内海沿いに位置する歴史と自然が調和したまちで、清流・錦川の沿岸を中心に文化が発展してきました。特に錦川下流域においては、世界文化遺産登録を目指す「名勝・錦帯橋」や「岩国城」が象徴するとおり城下町の風情が残っており、国の重要文化的景観に選定されています。
岩国市の360度動画では、錦川の清らかな流れや緑豊かな山々、鵜飼遊覧船から望む錦帯橋、錦川が流れ込む瀬戸内海を体験できます。ぜひ、いろいろな角度から岩国市の魅力をリアルに感じてください。
石川県羽咋市
石川県羽咋市は、能登半島の入り口に位置します。日本で唯一車で走れる砂浜「千里浜なぎさドライブウェイ」や神子原の棚田、能登國一宮氣多大社など、豊かな自然と歴史文化が共存しています。
動画では、五重塔を含む重要文化財である妙成寺を360度カメラで撮影しています。通常は見学できない建物の内部も特別に公開している点がポイントで、「ちょっと行ってみようかな?」と思わせる動画に仕上がっています。なお、動画は、「デジハクイ(羽咋市デジタル博物館)」にて掲載されています。
大阪府大阪市中央区
※制作・著作:株式会社サイバー・クラフト・大阪市(ムビサクにより制作されたものではありません)
大阪市中央区は、大阪の中心部に位置し、行政・経済・商業の要所として発展したエリアです。大阪城や難波宮跡、船場、心斎橋など歴史と現代が融合する地域で、大手企業の本社も多く集まります。
VR動画では、大阪ミナミの魅力を伝えています。中央区の南側を中心とする繁華街で、道頓堀・心斎橋・難波エリアが含まれます。とんぼりリバーウォークのある道頓堀川沿いは、昼夜問わず観光客と地元民で賑わい、たこ焼きや串カツなどのグルメ、劇場、ファッションストリートまで、活気あふれる大阪らしさを象徴する地域です。
長野県上伊那郡箕輪町
長野県上伊那郡箕輪町は、信州南部の伊那谷に広がる自然豊かな町です。東を伊那山地、西を中央アルプスに挟まれ、天竜川をはさんだ段丘上に広がります。水田・果樹園・畑があり、リンゴやブドウ、蕎麦を栽培する農業が盛んです。
360度動画では、箕輪町の代表的な観光スポットである「赤そばの里」を紹介しています。国内では珍しい赤い花の蕎麦が咲き誇る風景で、例年9月下旬から10月上旬にかけて「赤そばの里祭り」が開催されます。満開時には一面がピンク色の絨毯のようになる様子が動画で体験できます。
茨城県稲敷郡阿見町
阿見町は茨城県南部の稲敷郡に属し、県南地域の土浦市などとともに都市圏を構成しています。豊かな自然として霞ヶ浦や筑波山の美しい風景が広がり、住宅地の開発や工業団地の整備も進む一方、教育・医療機関やアウトレットなど都市機能も充実しています。また、予科練(海軍飛行予科練習生)ゆかりの歴史も特徴的です。
阿見町では、あみ観光協会が制作したPRコンテンツとして360度動画を配信しています。「まいあみ・まいつき・まちあるき」というテーマで、まいあみアンバサダーと公式キャラクターの「あみっぺ」が町内の見どころを楽しく紹介します。ブルーベリー狩りなど季節の体験を、VRゴーグルを使って臨場感のある仕様となっています。
鹿児島県

引用:鹿児島県「VR鹿児島城~よみがえる薩摩の館と城下町~」
鹿児島県は九州地方の最南端に位置する県で、県庁所在地は鹿児島市です。桜島や霧島、種子島宇宙センター、世界自然遺産の屋久島、奄美大島など多様な自然・文化資源を誇ります。特に薩摩藩として幕末・明治維新期の歴史に果たした大きな役割は、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」として保全されています。
鹿児島県では、鹿児島城VRアプリ「VR鹿児島城~よみがえる薩摩の館と城下町~」を配信しています。鹿児島城(鶴丸城)の姿をVRやARで体験できる無料アプリです。360度の復元CG映像で城や城下町を仮想体験でき、スポットごとの音声解説も充実しています。歴史上の人物とのAR記念撮影や攻城ゲーム、鹿児島歴史クイズなど、楽しみながら学べる機能が揃っています。
大阪府羽曳野市
羽曳野市は大阪府南東部、南河内地域に位置する市で、大阪市への通勤圏内にある住宅都市です。市内には世界文化遺産「百舌鳥・古市古墳群」の構成資産である応神天皇陵古墳や白鳥陵古墳など多数の古墳が点在し、古代史が息づく風景が魅力です。
羽曳野市では、日本最古の官道とされる竹内街道・横大路(大道)の魅力を伝えるため、360度VR動画を制作しました。竹内街道沿い、特に市内の古道や周辺景観を臨場感たっぷりに体験できる映像です。
動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、自治体向け動画における豊富な制作実績があります。
無料相談も承っております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
自治体のVR・360度動画に関するよくあるご質問
自治体のVR・360度動画についてのご質問はかなり多くいただきます。その中から、頻度の高いものへの回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
VRのメリットは何ですか?
- VRのメリットは、現実では体験が難しい状況や場所を、あたかもそこにいるかのように体感できる点にあります。例えば、遠隔地の観光地を自宅にいながら360度映像で巡ることができたり、災害現場の再現映像で避難訓練を行ったりすることが可能です。教育や医療、製造業などでも導入が進んでおり実践的な学びができます。
VRのデメリットは何ですか?
- VRのデメリットとしては、まず専用のゴーグルや機材が必要であり、導入にコストがかかる点が挙げられます。また、長時間の使用によって「VR酔い」と呼ばれる不快感を覚える人もおり、特に映像の動きと身体の感覚にズレがある場合は注意が必要です。また、没入しすぎて現実との境界が曖昧になるリスクもあります。
VRとメタバースの違いは何ですか?
- VRは「仮想現実」を意味し、ゴーグルなどを装着して、没入型の仮想空間を体験する技術そのものを指します。一方、メタバースはその技術を活用して構築された「多人数参加型の仮想空間」の概念です。例えば、VRが一人で仮想美術館を歩く体験だとすれば、メタバースは他の人のアバターと一緒に展示を鑑賞できます。
まとめ

VR(バーチャル・リアリティ)とは、仮想空間をあたかも現実のように体験できる技術のことを指します。観光地の風景を360度で再現することで、現地に行かずともその場の雰囲気を味わえる仕組みが実現します。教育、医療、建築など多分野で導入が進むなか、自治体においても住民サービスや地域活性化を目的とした活用が広がりつつあります。
自治体がVR動画を制作する際のポイントとしては、目的やターゲットを明確にして、「体験」を重視した没入感を与えることが大切です。また、撮影・編集は専門家に依頼することもよいでしょう。
なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、自治体向け動画における豊富な制作実績があります。
無料相談も承っております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

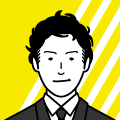



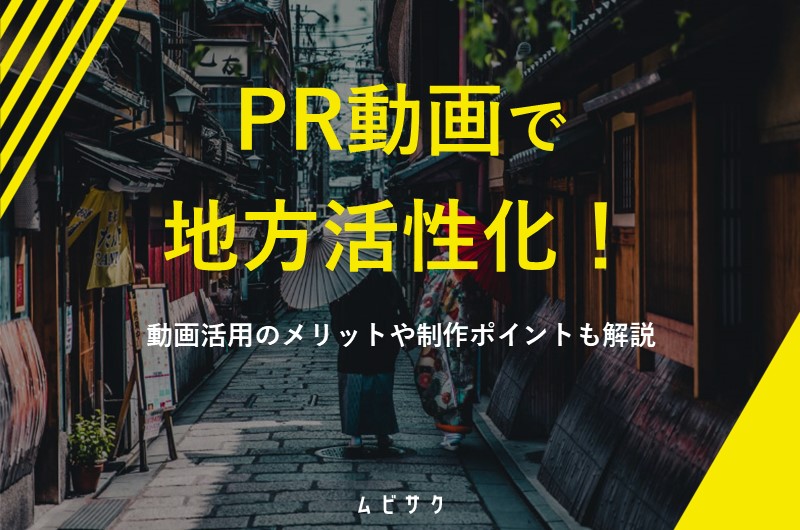


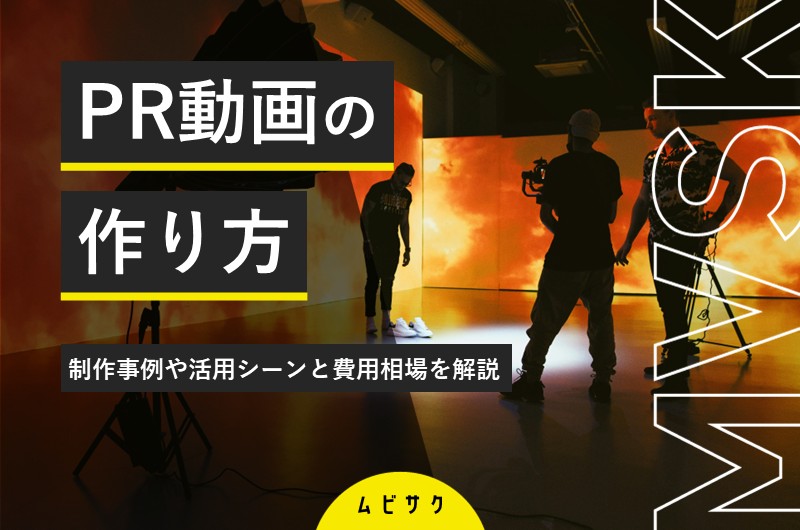

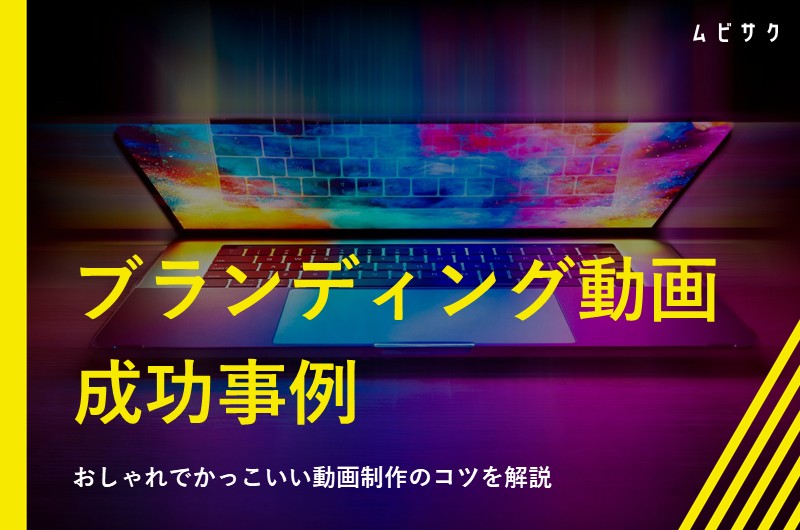
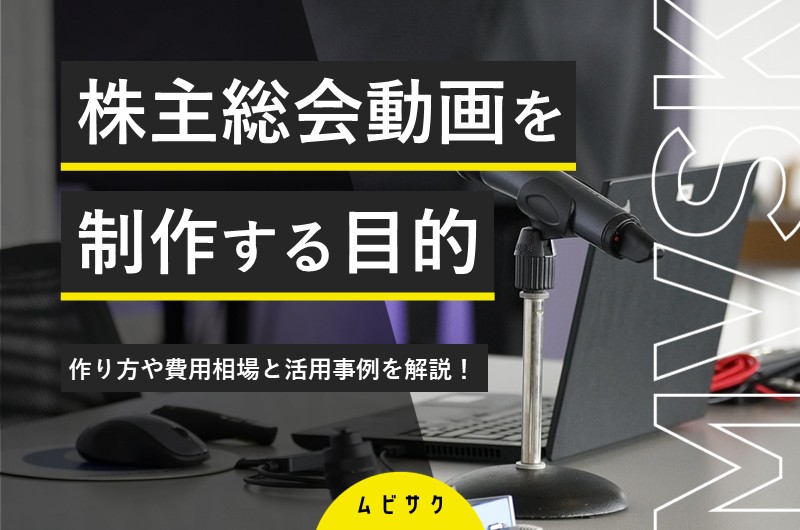
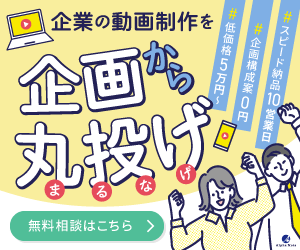


 03-5909-3939
03-5909-3939