プロモーション・PR動画とは、広報活動に用いる動画のことです。採用活動や会社説明会、セミナー、展示会などで自社をPRするときには、動画を活用するとより効果的です。しかし、動画を効果的なものにするにはいくつかのポイントを押さえておかなければなりません。
そこで、本記事ではプロモーション・PR動画を依頼・外注する際にかかる費用相場を解説します。自社のブランドやビジネスの内容、イメージに合ったPR動画を作成し、多くの人に認知してもらいましょう。
動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、企業紹介動画の豊富な制作実績があります。動画制作を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。
ムビサクの企業・団体のPR動画制作について詳しく知りたい方はこちら
- プロモーション・PR動画の制作費用相場
- コストを抑えて効果的なPR動画を制作するコツ
- プロモーション・PR動画の制作を依頼・外注するメリット
目次
動画制作でこんなお悩みありませんか?
- 動画制作を考えているがどうすればよいかわからない
- 急いで動画を作りたいが方法がわからない
- 高品質な動画を制作したいが自社では難しい…
\ スピーディーに高品質な動画を作るならムビサク /
無料で相談・問い合わせるプロモーション・PR動画における制作費用の相場表
プロモーション・PR動画の依頼・外注にかかる費用相場は、一般的に10万円~200万円程度です。ただし、表現方法や動画の種類、動画尺によっても大きく異なります。また、依頼する制作会社によって異なります。ここでは、一般的なPR動画の制作費用の相場をまとめます。
| プロモーション・PR動画の種類 | 依頼・外注にかかる費用相場 |
|---|---|
| 展示会・説明会動画 | 40万円~200万円 |
| 自社オウンドメディア動画 | 30万円~200万円 |
| YouTube動画 | 40万円~100万円 |
| 採用関連イベント動画 | 50万円~200万円 |
| 株主総会動画 | 30万円~200万円 |
| 社内報掲載動画 | 20万円~100万円 |
| 商品・サービスPR動画 | 30万円~100万円 |
| ブランディング動画 | 200万円~400万円 |
| インタビュー動画 | 20万円~200万円 |
| WEB動画広告 | 10万円〜200万円 |
| テレビCM | 100万円~400万円 |
また、PR動画の制作費用の相場は、アニメーション動画にするか、実写動画にするかによっても費用が異なります。
| プロモーション・PR動画の表現方法 | 依頼・外注にかかる費用相場 |
|---|---|
| アニメーション | 5万円~100万円 |
| 実写 | 30万円〜200万円 |
動画の種類や、アニメーションか実写によって、費用が異なる理由は、工数や規模が影響します。例えば、社内報として、簡単なお知らせ用のPR動画を配信するのであれば、演出にそこまでコストをかける必要もありません。そのため、比較的安価に制作することが可能です。
一方で、ブランディング動画やテレビCM、展示会等のイベントで上映する動画は、企業の顔になります。オリジナルのキャラクターを作成したり、プロの演者を起用して撮影チームを組んで制作することも多くあります。結果として、撮影やイラスト制作に含まれる分の工数や人件費が上乗せされるため、比較的に高額な動画になります。
【事例あり】PR動画の依頼・外注にかかる実際の費用
これまでにムビサクが制作したPR動画の制作事例を紹介します。他の会社の成功例を確認することで、PR動画のイメージを深めることができます。どのような動画が完成するのかイメージしにくいと感じている人は、ぜひひととおりチェックしてみてください。
- 株式会社アズ企画設計
- 株式会社アブレイズパートナーズ
- アナザーレーン株式会社
- 株式会社Gakken
- スマサテ株式会社
- 株式会社コーユービジネス
- セルプロモート株式会社
それぞれの動画を視聴することで、企業紹介動画とはどのようなものか、何を紹介すればよいのかがわかるでしょう。
株式会社アズ企画設計
事例:新卒・中途採用動画アニメーション
| 動画の配信場所 | 就活関連イベント |
|---|---|
| 費用 | 50万円~ |
ポイント:採用活動に使用する目的で試作した企業紹介動画です。企業の経営方針やコンセプトを明確に掲げたうえで、どのような成果を出したかに言及しているためイメージしやすい点がポイントです。
不動産の買付から売却までの流れも簡潔に紹介していて、ビジネススタイルを理解しやすいのも特徴です。求職者が知りたい「会社の概要」「業績」「ビジネススタイル」「歴史」をコンパクトにまとめています。
約2分の動画ですが、一度視聴するとどのようなビジネスを営んでいる企業なのかある程度理解できるでしょう。
動画では、1989年の創業から展開されてきた、不動産売買や賃貸、管理事業など提供しているサービスの全体像を紹介しています。明るいテイストのイラストを用いて、賃貸事業における空室物件や遊休地の再生に取り組む様子も表現することで、企業のイメージアップにもつながります。
また、企業のビジョンである「空室のない元気な街をつくる」というコンセプトを視覚的に伝えるような構成の動画です。ターゲットである求職者にビジョンや、事業領域を理解してもらうことで、入社後のギャップから起こる早期離職を防ぐことも狙いです。
株式会社アブレイズパートナーズ
事例:キャラクターを用いたアニメーション動画
| 動画の配信場所 | YouTube |
|---|---|
| 費用 | 10万円~30万円 |
ポイント:株式会社アブレイズパートナーズが手がけている賃貸管理サービスを紹介する動画です。冒頭で他者の類似サービスと比較し、自社のサービスが価格面で強みがあることをアピールしている点がポイントです。
動画内で集客力や客付力をアピールすることで、その懸念を払拭していることがわかるでしょう。高い入居率を維持していること、充実した管理サービスを提供していることにも触れています。
賃貸管理サービスを探しているオーナーにとって気になる情報がコンパクトにまとめられており、簡潔かつ理解しやすい仕上がりです。
また、動画の制作に対して、不動産管理事業を展開していることが知られていないことも課題でした。そこで、キャッチコピーやイメージコピーで世界観を伝えるのではなく、「ずっと賃貸月額管理料0円」という強い言葉のセールスコピーでまとめました。
加えて、ターゲットに安心してもらえるように、サービス提供ができる理由やエビデンスにも振れる構成にしてあります。
アナザーレーン株式会社
事例:就活生に向けた会社説明動画
| 動画の配信場所 | 就活関連イベント |
|---|---|
| 費用 | 5万円~10万円 |
ポイント:アナザーレーン株式会社にて新卒採用向けの会社説明会で上映する目的で制作した動画です。わずか20秒の短い動画ですが、求職者が気になるポイントとして社員の構成や勤続年数、業務時間を紹介している点がポイントです。
実際に会社説明会を開催するときには、仕事内容や社員インタビューなどをまとめた別の動画と併用しても効果的といえるでしょう。短い動画に伝えたいことをコンパクトにまとめると印象に残りやすいため、効果的な方法です。
動画では、男女比や平均年齢など社内で実施したアンケート結果をもとに、伝わりやすいインフォグラフィックアニメーションで表現しています。採用サイトなどのオンライン上での利用だけではなく、会社説明会などのオフランでの就活関連イベントで利用されています。
加えて、動画のスピード感もポイントです。会社説明会では、動画によって求職者の興味を引くことは大切ですが、あまり長い尺の動画になってしまうと、集中力が途切れてしまい、印象に残らない動画になってしまうこともあります。スピード感のあるエフェクトで要点を絞ってまとめることで、最後まで視聴してもらいやすい構成にしています。
株式会社Gakken
事例:絵本「ちっちゃな おさかなちゃん」YouTubeプロモーション動画
| 動画の配信場所 | YouTube |
|---|---|
| 費用 | 30万円~50万円 |
ポイント:株式会社Gakkenが販売する絵本「ちっちゃな おさかなちゃん」のプロモーションとして公開されたPR動画です。YouTubeと自社オウンドメディアでの配信を目的に制作しました。絵本のイラストを使って、世界観を統一した演出がポイントです。
また、絵本のページがめくられるようなアニメーションと効果音で、絵本の世界観を忠実に再現することによって、親子で一緒に読みたいと感じる構成にしています。動画の後半では、世界中の購入者から寄せられた口コミを組み込むことで、作品に対する安心感も訴求されています。
加えて、この動画はPR動画であることに加えて、ブランディング要素も担った動画です。ブランドのもつコンセプトを大切して、絵本のストーリーに近い構成も特徴的です。
映像だけではなく、優しいBGMや海のなかで泡がはじける効果音、温かみのあるフォントなど細部にまでこだわった作品です。
スマサテ株式会社
事例:不動産査定システムのサービス紹介動画
| 動画の配信場所 | 展示会・説明会 |
|---|---|
| 費用 | 30万円~50万円 |
ポイント:不動産のAI査定システム「スマサテ」を提供するスマサテ株式会社のPR動画です。展示会出展にあわせて制作した動画ですが、もともとは、以前に訪れた展示会の他社ブースで動画を有効活用していたことがきっかけでした。
動画では、サービス名を強調している点がポイントです。冒頭は、クイズ形式にすることで来場者の足を止めて、サービス名を伝えることで、印象に残る構成になっています。
また、サービス名とともにロボットのキャラクターが登場することで、インパクトのある動画になっています。キャラクターの声も特徴的なナレーションで、目だけではなく耳にも記憶に残ることを狙いました。
加えて、展示会の出展ブースに上映する作品として、中間部のパートからは、具体的なサービスの紹介が始まります。機能や特徴をアニメーションで表現することで、営業スタッフが説明する手間を省くことにもつながります。
株式会社コーユービジネス
事例:展示会ブースでの商品紹介動画
| 動画の配信場所 | 展示会・説明会 |
|---|---|
| 費用 | 50万円~ |
ポイント:株式会社コーユービジネスが提供する、AR技術を活用したスマートグラス「ロジスグラス」のPR動画です。物流業務の効率化を進めるBtoB商品としての認知度拡大を目的としていました。
展示会で流す動画ということで、冒頭からインパクトのあるアニメーションにしたことがポイントです。2024年問題への解決策として「ロジスグラス」がハンズフリー革命を巻き起こす様子を、ダイナミックに表現しました。
スマートグラスという形のある商品ではありますが、商品コードを認識する仕組みや保管場所を瞬時に確認できる様子は、実写の動画では表現がしづらいものです。そこで、スマートグラスを着用したキャラクターを用いることで、実際の作業のイメージを具体的に伝わるように演出しています。
また、展示会では音声も流せるため、BGMや効果音にもこだわりました。ロボットアニメなどに用いられるような機械的な効果音を組み合わせることで、近未来感も表現しています。
セルプロモート株式会社
事例:採用活動におけるオンボーディング動画
| 動画の配信場所 | 自社オウンドメディア |
|---|---|
| 費用 | 30万円~50万円 |
ポイント:セルプロモート株式会社では、自社オウンドメディアとして採用メディアを運営しています。採用メディアへの掲載だけではなく、エンジニアに向けた中途採用の面接時や会社説明会などの採用イベントで配信される動画です。動画では、セルプロモート株式会社での選考ステップから入社後のイメージが掴めるようなアニメーションで表現されています。
社員インタビューは実写動画を用いられることも多くありますが、キャリア育成などのオンボーディングは説明が難いこともあります。イラストやアニメーションを効果的に活用することで、伝わりやすい動画になっています。
また、求人広告動画ではないため、比較的長い動画尺である点も特徴的です。動画の前半と後半で伝えたいメッセージが分かれており、前半パートでは、入社までのステップが伝えられています。一方で、後半パートでは、セルプロモート株式会社でのエンジニアに対する人事評価がどのように決まっていくのか、具体的に示しています。
採用動画は、入社後のギャップを防ぎ、新人の早期離職率を改善する効果があります。アニメーションを用いることで、不透明になりやすいキャリア形成を可視化できるため、求職者には安心して入社を決めてもらうことにもつながるでしょう。
コストを抑えて効果的なPR動画を制作するコツ

PR動画を制作する目的が定まったら、具体的な制作活動をはじめましょう。制作活動に取り組むときは、途中で軸がブレないように注意しながら進めることが大切です。ここでは、PR動画の作り方のコツをまとめて解説します。
- 企画(目的・ターゲット・訴求内容)を明確にする
- ターゲットに合わせた構成を決める
- コンセプトにあわせて映像素材を撮影する
- 編集で伝えたいメッセージを目立たせる
- 伝えたいメッセージをひとつに絞る
- 流行や話題性を意識する
- 視聴者が自分ごと化しやすくする
この順番で制作を進めることで、途中で目的を見失ったり一体感がない動画に仕上がったりすることを防げるでしょう。
企画(目的・ターゲット・訴求内容)を明確にする
PR動画を作ると決めたら、具体的な企画を決めましょう。企画段階では、以下のことを決定します。
- 動画の制作目的(展示会用・SNS広告用など)
- ターゲット(BtoB・BtoCなど)
- 訴求内容(伝えるメッセージ)
この3つを定めることで、動画の軸となるポイントが決まります。次以降の段階では、企画段階で決まったことに基づいて制作を進めましょう。
ターゲットに合わせた構成を決める
次に考えるのは具体的な構成です。目的によって多少の差があるものの、PR動画では以下の構成で設計するのがおすすめです。
- 興味を引きつけるオープニング
- 視聴者の課題提起
- メッセージの伝達
- 視聴者に対するメリット提示
- エンディング
視聴者が抱えている課題を掘り起こし、自社のビジネスがどのように役立つかを提示できれば印象に残りやすいでしょう。「一度見たら忘れない」と感じるインパクトも欠かせません。「どうしたら視聴者に覚えてもらえるか」を考えるのがおすすめです。
コンセプトにあわせて映像素材を撮影する
構成が明確に決まったら、映像素材を撮影しましょう。動画のコンセプトや伝えたいメッセージにもとづき、実写映像やCG映像、アニメーションなどの必要な素材を準備します。
映像素材を準備するときは、画質を重視してください。画質が悪いとチープな印象の動画に仕上がるため、自社に対するイメージが悪くなる可能性があります。十分な画質の映像を撮影することで、十分なクオリティの動画に仕上がります。
編集で伝えたいメッセージを目立たせる
映像素材を準備したら、編集作業を行います。編集では撮影した映像素材を構成にしたがって並べ、音響効果やエフェクトなどを追加しながら1本の動画に仕上げましょう。
編集も動画のクオリティに直結する重要な作業です。伝えたいメッセージを目立たせるために字幕を挿入したり、インパクトがある効果音を用いたりするなど、どうすれば効果的な動画になるか考えながら編集します。
編集は手間がかかる工程ですが、仕上がりに大きく影響するため手を抜かないことをおすすめします。
なお、一般的な動画制作の流れについては下記で詳しく解説しています。
伝えたいメッセージをひとつに絞る
PR動画を制作する際のコツとして重要な点は、伝えたいメッセージをひとつに絞ることです。
PR動画は限られた時間内で視聴者にインパクトを与える必要があるため、複数のメッセージを詰め込みすぎると、どれも中途半端に終わってしまう可能性があります。伝えたい内容を明確にし、シンプルで強力なストーリーを作り上げることで、視聴者にしっかりと印象を残すことができます。
また、メッセージが一貫していると、視聴者が動画を見終わった後に情報を覚えてもらえるため、ブランドや商品の認知度向上につながります。メッセージはシンプルなほうが、記憶に残りやすくなります。さらに、明確なメッセージがあることで、動画のコンセプトや映像表現も一貫性を持たせやすくなり、ハイクオリティな動画コンテンツにもつながります。
流行や話題性を意識する
流行や話題性を意識することも、PR動画を成功させるうえで重要です。
若者をはじめとした視聴者は常に新しいトレンドや社会の話題に敏感なため、流行を反映させたコンテンツを制作することで、自然と注目を集めることができます。例えば、流行している音楽やおしゃれな映像表現、話題の人物、面白いアイデアをうまく取り入れることで、視聴者の興味を引き、SNSなどでの拡散力を高める効果が期待できます。
ただし、流行に流されすぎず、ブランドの価値やメッセージとの整合性を保つことも大切です。トレンドを取り入れつつも、オリジナリティをしっかりと持たせたPR動画にしていきましょう。また、流行は瞬時に切替わるため、時期を逃さずスピーディに対応する柔軟性も大切です。
視聴者が自分ごと化しやすくする
視聴者が自分ごと化しやすい内容にすることもPR動画では欠かせません。
視聴者にとって、単なる一方的な情報の提供ではなく、自分自身の問題やニーズに結びつくものであると感じてもらえると、より強く関心を引くことができます。例えば、共感を呼ぶストーリーや日常的なシーンを取り入れることで、視聴者はその動画に自分を投影しやすくなります。
また、視聴者が具体的に行動に移せるようなメッセージやアクションを含めると、動画の目的である購買意欲やサービス利用の促進に効果的です。そのため、視聴者の視点に立ったコンテンツ作りが、PR動画の成功につながっていくでしょう。さらに、視聴者との感情的なつながりを構築できれば、ブランドや商品への信頼感を高め、長期的なファンの獲得にも効果的です。
PR動画の制作を依頼・外注するメリット

PR動画の制作を依頼・外注することには、次のようなメリットがあります。これらのポイントにメリットを感じるのであれば、積極的にPR動画を活用しましょう。
- 視聴者に覚えてもらいやすくなる
- 表現の幅が広がる
- 情報の伝達効率がよい
- SNSで拡散されやすい
- 抽象的な内容を伝えやすい
- 時間や場所を選ばない
それぞれどのようなポイントがメリットになるのかを解説します。動画の活用を検討しているのであれば、ぜひチェックしてみてください。
視聴者に覚えてもらいやすくなる
動画は映像と音響でユーザーの視覚・聴覚に訴えるため、印象に残りやすいのがメリットです。パンフレットやパネルなどの資料に加えて、一度見ただけでも覚えてもらいやすいメディアといえるでしょう。
短時間の動画でも印象に残りやすいものを制作すれば、自社のことを覚えてもらうのに役立ちます。とくにベンチャー企業やスタートアップ企業は、認知度を高めることが重要です。動画を効果的に活用し、認知度アップに取り組むとよいでしょう。
表現の幅が広がる
さまざまな技法を使用できるため、表現の幅が広がるのも動画のメリットです。一言で動画といっても、制作に使用する技法は以下のようにさまざまです。
- 実写
- アニメーション
- CG
どれかひとつに限ることもできれば、複数の技法を組み合わせることも可能です。コンセプトや目的に応じてさまざまな技法を活用すれば、より豊かな表現ができるようになるでしょう。
映像やテキストをベースにした展示物やパンフレットに比べて表現の幅が広く、自社ならではの個性を出せるのがメリットです。
なお、表現の幅が拾いPR動画は、企業だけではなく、行政や地方自治体、観光地のプロモーションにも活用されています。地方活性化にPR動画を活用するメリットや制作のポイントについては、以下の記事も参考にしてください。
情報の伝達効率がよい
短時間で効率的に情報を伝えたいと考えている場合、動画を活用するのがおすすめです。たとえば、1分間の動画と1分で読めるパンフレットを比較すると、伝達できる情報は動画のほうが圧倒的に多くなります。
視聴者も集中してテキストを追い掛ける必要がないため、負荷が少ないといえるでしょう。動画は多くの人の目に留まるだけでなく、限られた時間で効率的に情報を伝達できる有用なメディアです。
参考:アメリカのJames L. McQuivey博士の研究
SNSで拡散されやすい
PR動画を制作するメリットとして、SNSでの拡散力が挙げられます。
現代では、SNSが情報発信の中心的な役割を果たしており、特に動画コンテンツは視覚的でインパクトが強いため、多くのユーザーにシェアされやすい特徴があります。動画は静止画やテキストに比べて短時間で多くの情報を伝えることができるため、ユーザーの興味を引きやすく、拡散効果が高まります。
また、SNSのアルゴリズムによっては、動画はより多くのフォロワーにリーチしやすくなり、結果としてブランドの認知度向上につながります。さらに、SNS上での反応やコメントを通じて双方向のコミュニケーションが可能になり、顧客との関係も深まることで、より長期的なブランド価値の向上が期待できます。
抽象的な内容を伝えやすい
PR動画は抽象的なメッセージを視覚的に伝えるのに優れているというメリットもあります。
文章や写真では伝わりにくいコンセプトや雰囲気、感情を、映像や音声を通じて効果的に表現することができます。特に、ブランドの理念や商品のユニークな特徴を強調したい場合には効果的です。動画を用いることで視聴者に感覚的に理解させることができ、結果として深い共感や興味を引き出すことが可能です。
例えば、ストーリーを通じて複雑なメッセージをよりシンプルに伝えることができます。視聴者の感情に訴えかけ、商品やサービスに対する印象を強めることにつながるでしょう。視覚と音の相乗効果は、文字や写真などに比べて説得力が高まります。
時間・場所を選ばない
PR動画は時間や場所を問わず視聴できる点もメリットです。
スマホやタブレットの普及により、通勤中やちょっとした休憩時間など、いつでもどこでも動画を楽しむことができる環境が整ってきています。そのため、従来の広告に比べて、より多くのシチュエーションで視聴される機会が増え、幅広いターゲット層にアプローチすることが可能となります。
動画が提供する利便性は、忙しい現代人にとって非常に魅力的です。また、オンデマンドで視聴可能なため、ユーザーが自分のペースで情報を受け取ることができるのも、視聴体験の質を高める要素のひとつと言えるでしょう。
PR動画の制作を依頼・外注するデメリット

PR動画の制作を依頼・外注する際にはデメリットもあります。
- 内製するよりコストがかかる
- 社内に動画制作のノウハウが蓄積されない
- コミュニケーションの時間がかかる
ここでは、それぞれのデメリットと注意すべき点について具体的に解説します。
内製するよりコストがかかる
PR動画を外注すると、企画の立案やシナリオ作成、撮影、編集といった工程ごとに専門的な人材が関わるため、どうしても一定の費用が発生します。
例えば、自社で社員が簡単な動画を作る場合は人件費の範囲で済みますが、制作会社に依頼する場合はクオリティを担保するために機材や人材に応じた費用が加算されます。その結果、限られた予算を有効に配分したい企業にとっては負担となりやすく、社内の他施策とのバランスを考える必要があります。
社内に動画制作のノウハウが蓄積されない
外部に依頼して動画を制作すると、完成度の高いコンテンツを得られる一方で、社内に知識やスキルが残らないという側面があります。
例えば、映像の編集技術やシナリオ構築の方法を内製で学んでいれば、次回以降は効率的に制作を進めることができます。しかし、外注を繰り返すと担当者が経験を積む機会が失われます。そのため、長期的に社内で動画活用を広げたいと考える企業にとっては、社内のノウハウが課題となる可能性があります。
コミュニケーションの時間がかかる
制作会社に依頼する場合、コンセプトやターゲット層、訴求したいメッセージを正確に共有するために打ち合わせを重ねる必要があります。
例えば、完成イメージが社内で固まっていない状態で依頼すると、制作過程での修正や追加説明が増え、時間的なロスにつながります。さらに、制作側の表現手法と依頼側の意向にずれが生じれば、合意形成までに追加の調整が必要となることもあります。そのため、完成までに想定以上のコミュニケーションコストを要する点がデメリットといえます。
PR動画を依頼・外注する際の事前準備のチェック項目

PR動画を依頼・外注する際の事前準備のチェック項目は「目的」「予算」「納期」です。事前準備が不足していると、打ち合わせが長引いたり、完成後に修正が増えたりする原因になりがちです。目的や予算、納期が明確になっていれば、制作会社からより的確な提案を受けやすくなります。ここでは、PR動画をスムーズに制作するために、依頼前に確認しておきたいチェック項目を紹介します。
チェック項目1:目的
PR動画を依頼・外注する前に、まず整理しておきたいのが制作の目的です。動画を通じて何を伝え、視聴者にどのような行動を取ってほしいのかを明確にすることで、企画や構成の軸が定まります。
例えば、展示会で足を止めてもらうことが目的なのか、Webサイトでサービス理解を深めることが目的なのかによって、動画の尺や演出は大きく変わります。目的が曖昧なままだと、情報を詰め込みすぎたり、誰に向けた動画なのか分からなくなったりしやすくなります。その結果、完成後に修正が増え、時間やコストが余計にかかるケースもあります。依頼前に目的を言語化しておくことで、制作会社との認識のずれを防ぎ、意図に沿ったPR動画を作りやすくなります。
チェック項目2:予算
PR動画を外注する際は、あらかじめ想定できる予算の範囲を決めておくことが重要です。制作費用は動画の尺や表現方法、撮影の有無によって変動するため、上限が決まっていないと見積もりの比較が難しくなります。
例えば、アニメーション中心で情報を整理した動画と、実写撮影を伴う動画では必要な工数が異なり、費用感にも差が出ます。予算を伝えずに依頼すると、想定以上の提案が出てきたり、逆に要望を十分に反映できなかったりすることもあります。あらかじめ予算感を共有しておくことで、その範囲内で実現できる最適な構成や演出を提案してもらいやすくなり、現実的な制作計画を立てることにつながります。
チェック項目3:納期
PR動画を活用するタイミングが決まっている場合、納期の整理も欠かせません。動画制作には企画、構成、素材準備、編集など複数の工程があり、一定の制作期間が必要になります。
例えば、展示会や採用イベントに合わせて動画を使用する場合、公開日から逆算して余裕をもったスケジュールを組むことが大切です。納期があいまいなままだと、修正対応が難しくなったり、仕上がりの質に影響が出たりする可能性があります。また、社内確認にかかる時間も考慮しておく必要があります。事前に希望納期と使用開始日を明確に伝えることで、制作会社側も現実的なスケジュールを組みやすくなり、トラブルを防ぎながらスムーズに進行できます。
PR動画の制作方法と依頼・外注先の選び方

PR動画を制作するといっても、前例がなかったり動画編集のスキルを持っている人材がいなかったりなどの理由で、難しく感じることもあるのではないでしょうか?ここでは、PR動画を制作する方法として、以下の4つを紹介します。
- 自社で制作する
- 個人のクリエイターに依頼する
- マッチングサイトやCtoCプラットフォームで探す
- 制作会社に依頼する
それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説するため、自社の状況に応じて適切な方法を選択しましょう。
自社で制作する
自社でPR動画を制作する方法は、社内にある情報を活かしながら柔軟に進められる点が特徴です。例えば、サービスの魅力を理解している社員が企画や撮影に関わることで、現場の温度感を反映した表現がしやすくなります。
また、制作の進行を自社で管理できるため、急な修正や方向転換にも対応しやすいメリットがあります。一方で、制作に必要な機材や編集スキルをどの程度持っているかが完成度に影響するため、事前に社内体制を整えることが重要です。短期間で制作しようとすると業務との両立が負担になることもあるため、目的に応じて内製化の範囲を見極めることが求められます。
自社で制作するメリット
自社で制作するメリットは以下の3点です。
- 社内の理解を反映した動画を作りやすい
- 制作コストを抑えやすい
- 柔軟なスケジュール調整ができる
これらの要素は、社内の情報を深く把握している担当者が企画に関わることで生まれます。例えば、日々の業務で得た知見をそのまま構成に落とし込むことで、外部には伝わりにくい強みを自然に表現できます。
また、コスト面では外注費が発生しないため予算を調整しやすく、急な内容変更にも対応しやすい点が魅力です。制作期間を自由に調整できるため、複数の部署が関わるプロジェクトでも進行管理を行いやすいのも特徴です。
自社で制作するデメリット
自社で制作するデメリットは以下の3点です。
- 専門的なスキルが不足しやすい
- 完成までに時間がかかりやすい
- 品質が安定しにくい
企画から撮影、編集までを社内で行う場合、担当者の経験値が仕上がりを左右します。例えば、カメラ操作やアニメーション制作などの専門性が求められる工程があげられます。
慣れていない作業が多いと時間がかかり、業務負担が増えてしまうこともあります。また、担当者のスキルによって品質に差が出やすく、動画の目的に合わない表現になってしまう可能性もあります。内製化を進める際は、担当範囲と求めるクオリティのバランスを見極めることが重要です。
個人のクリエイターに依頼する
個人のクリエイターに依頼する方法は、柔軟な対応と独自の表現が得られる点が魅力です。例えば、アニメーションに強みを持つクリエイターに依頼すれば、企画の段階から世界観づくりに参加してもらえるため、個性的なPR動画に仕上げやすくなります。
制作会社に比べると費用が抑えられることも多く、短尺のプロモーションやSNS向け動画の制作にも適しています。一方で、スケジュール管理や品質の安定はクリエイター一人に依存するため、事前に実績やポートフォリオを確認し、コミュニケーション手段や納品方法などを明確にしておくことが大切です。
個人のクリエイターに依頼するメリット
個人のクリエイターに依頼するメリットは以下の3点です。
- 比較的コストを抑えやすい
- 柔軟でスピーディな対応が期待できる
- 個性的な表現を活かしやすい
個人で活動しているクリエイターは、例えば制作会社よりも工程の調整がしやすく、依頼者の意図を汲んだ細かい演出を提案してくれることがあります。
また、得意分野が明確なケースが多く、アニメーション特化やSNS動画に特化するなど、独自の発想で制作してもらえる点も魅力です。予算が限られていても相談しやすく、初めてPR動画を制作する企業にとって検討しやすい依頼方法といえます。
個人のクリエイターに依頼するデメリット
個人のクリエイターに依頼するデメリットは以下の3点です。
- 品質のばらつきが生じやすい
- 制作体制が一人に依存する
- 納期トラブルが起こりやすい
個人で活動している場合、例えば急なスケジュール変更や体調不良があった際に代替対応が難しい点があります。
また、実写・アニメーション・撮影など幅広い工程をこなす必要がある案件では、一人では十分に対応できない場合もあります。品質面でも得意・不得意の差が出やすいため、依頼前に過去の作品やレビューを確認し、制作範囲やスケジュールを明確にしたうえで進めることが欠かせません。
マッチングサイトやCtoCプラットフォームで探す
マッチングサイトやCtoCプラットフォームを利用する方法は、多数のクリエイターから自社の目的に合う人材を探せる点が特徴です。例えば、短尺のアニメーション動画を得意とする人や、展示会向けの実写撮影を専門にする人など、スキルの異なる制作者を比較しながら検討できます。
プロフィールや料金を事前に確認できるため、予算と目的に合わせた依頼がしやすいのもメリットです。一方で、クリエイターの実績や品質が一定ではないため、選定には時間がかかることがあります。そのため、依頼時にはコミュニケーション手段や納品形式を明確にすることも重要です。
マッチングサイトやCtoCプラットフォームで探すメリット
マッチングサイトやCtoCプラットフォームを利用するメリットは以下の3点です。
- 豊富な候補から制作者を選べる
- 予算に合わせた依頼がしやすい
- レビューや評価を参考に比較できる
多数のクリエイターが登録しているため、例えば予算に合わせて複数の見積もりを比較することができます。得意領域が明確なクリエイターも多く、アニメーション、実写、SNS動画など目的に応じた制作依頼がしやすい点も魅力です。
また、過去の評価を確認することで制作スタイルや対応の丁寧さを把握しやすく、初めて外注する場合でも検討しやすい方法といえます。
マッチングサイトやCtoCプラットフォームで探すデメリット
マッチングサイトやCtoCプラットフォームのデメリットは以下の3点です。
- 品質が安定しにくい
- 選定に時間がかかる
- コミュニケーションが複雑になりやすい
さまざまなクリエイターが登録しているため、例えばスキルや経験の差が大きく、仕上がりにばらつきが出る可能性があります。また、数多くの候補から選ぶ必要があるため、比較検討に時間を要する場合があります。
制作の進行もオンライン上のやり取りが中心となるため、認識のずれが起きるリスクもあります。依頼前にポートフォリオや制作範囲を丁寧に確認し、双方の役割を明確にして進めることが大切です。
制作会社に依頼する
制作会社に依頼する方法は、企画から撮影、編集までを一貫して任せられる点が特徴です。例えば、展示会向けや採用向けなど用途別に最適な構成を提案してもらえるため、目的に合わせた動画を安定した品質で制作できます。
また、複数の専門スタッフが関わるため、実写撮影やアニメーションなど多様な表現にも対応しやすく、社内では再現しにくい技術を取り入れられることもあります。一方で、外注費は一定の負担となるため、求めるクオリティと予算のバランスを明確にしたうえで依頼することが重要です。制作過程では丁寧なコミュニケーションが求められます。
制作会社に依頼するメリット
制作会社に依頼するメリットは以下の3点です。
- 安定した品質で制作してもらえる
- 専門的な技術を取り入れやすい
- 制作の負担を軽減できる
制作会社は、アニメーションや撮影など分業体制が整っているため、それぞれの工程を専門スタッフが担当します。そのため品質にばらつきが出にくく、完成イメージに近い動画を制作しやすい点が魅力です。
また、CGや高度な編集技術など、社内では対応が難しい表現にも柔軟に応じられます。制作工程を任せられるため、担当者の負担を減らしつつ、社内の業務に集中できる環境を作りやすい点もメリットです。
制作会社に依頼するデメリット
制作会社に依頼するデメリットは以下の3点です。
- 外注コストがかかる
- 情報共有に時間が必要になる
- 修正に追加費用が発生する場合がある
制作会社に依頼する場合、例えば撮影や編集に必要なスタッフが複数関わるため、一定の費用が発生します。また、ビジョンやターゲット像を伝えるために丁寧な打ち合わせが必要で、進行に時間がかかることもあります。
完成後の修正が多くなると追加費用が発生するケースがあるため、事前に仕様や構成を固めておくことが大切です。求めるクオリティと予算のバランスを意識しながら依頼内容を整理することが重要です。
また、PR動画の制作をプロに任せるのであれば、十分なスキルを有した制作会社を選ぶことが大切です。なお、はじめての動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。
ムビサクではアニメーションをフル活用した動画や撮影を伴う実写動画を制作しています。展示会向けや採用活動向けなど、用途に応じた動画を制作可能です。
また、ムビサクでは動画制作のご依頼を考えている人向けの無料相談を実施しています。
お気軽にお問い合わせください。
PR動画のよくあるご質問
PR動画についてのご質問はかなり多くいただきます。その中から、頻度の高いものへの回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
企業におけるPR動画とは何ですか?
- 企業におけるPR動画とは、企業やブランドにおける魅力や価値を伝える映像コンテンツです。商品やサービスの特徴を鮮明に表現し、視聴者に共感や信頼を喚起させます。効果的なツールとして、ターゲットを惹きつけ、ブランドの認知度や評判を高めます。
企業における採用動画のメリットは何ですか?
- 企業における採用動画のメリットは、魅力的な仕事環境や企業文化を伝え、優秀な人材を引き寄せることです。動画は視覚的かつ感情的なインパクトを与え、企業の魅力を具体的に伝えることができます。個別の従業員の声や成功事例を取り入れることで、信頼性を高めて競合企業と差別化することができます。また、社内の雰囲気や働く魅力を実感させ、応募者の関心を引く効果もあります。企業における採用動画は、効果的な採用活動に役立ち、適切な人材を獲得するための貴重なツールです。
PR動画の効果は何ですか?
- PR動画は、魅力的な映像表現とストーリー性によりブランド認知度を高め、共感と信頼を生み出す効果があります。PR動画は簡単に共有できるため拡散性も高く、ターゲット層の関心を引きブランドの強化につながります。
まとめ

PR動画は、社員や株主、消費者に自社について詳しく知ってもらうことを目的とした動画です。プロモーション・PR動画の依頼・外注にかかる費用相場は、一般的に10万円~200万円程度です。ただし、表現方法や動画の種類、動画尺によっても大きく異なります。また、依頼する制作会社によって異なります。そのため、どのようなメッセージを伝えたいのかを明確にし、目的に応じた動画を制作するとよいでしょう。
動画は短時間で効果的に情報を伝達できますが、効果的なものにするにはある程度の制作スキルが必要です。なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、自社に動画を制作できるスタッフがいない企業の方におすすめです。
ムビサクでは目的に応じて適切なPR動画を制作しています。以下のページから手軽にお問い合わせ頂けますので、ぜひご検討ください。

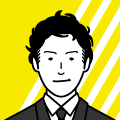

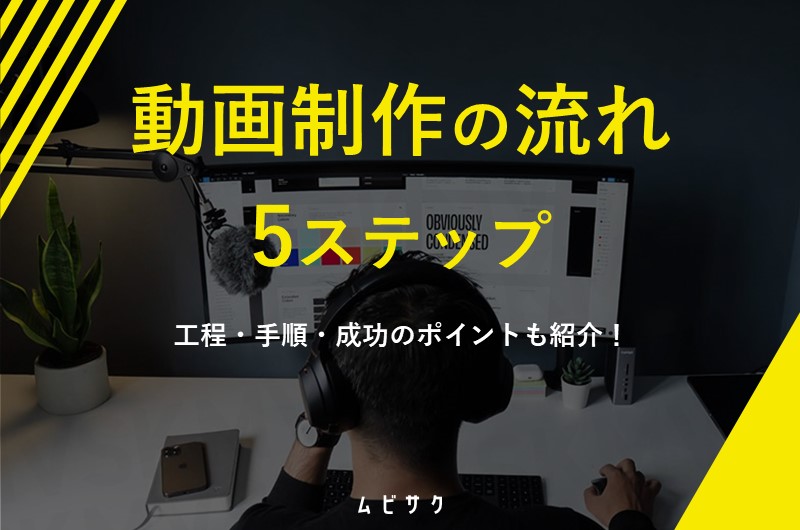
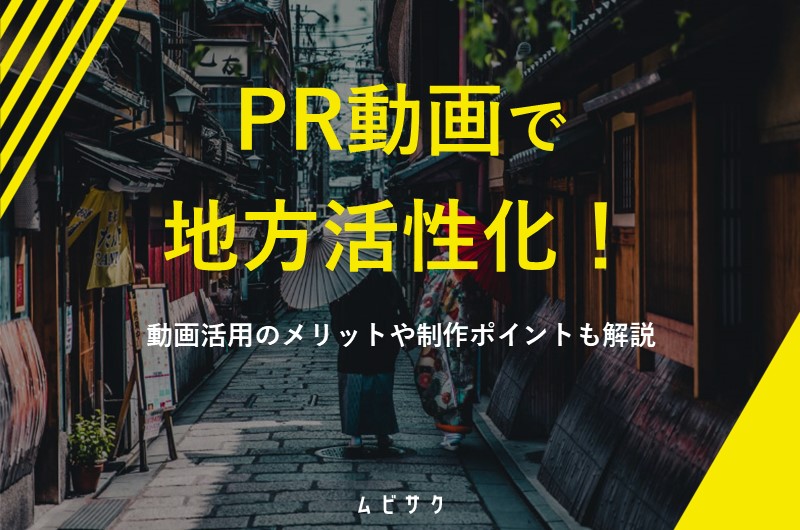

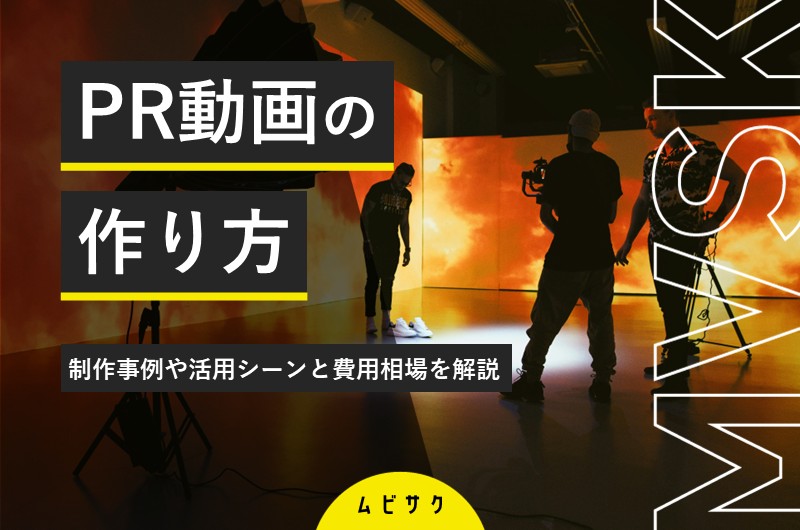

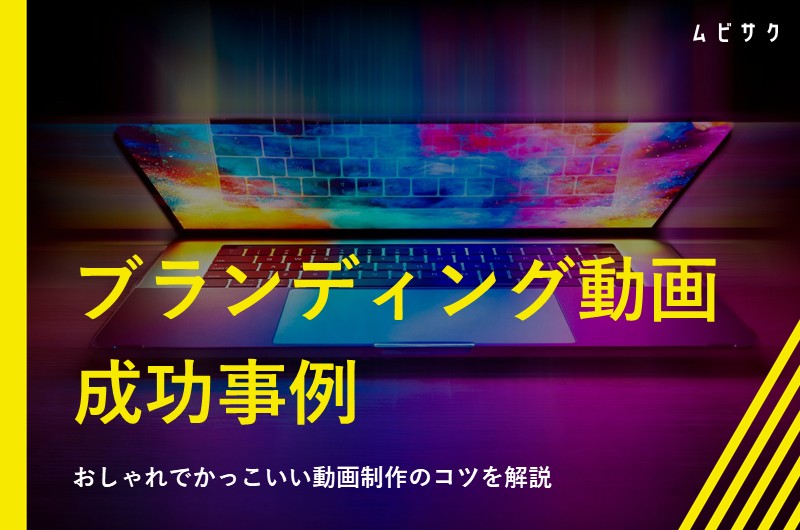
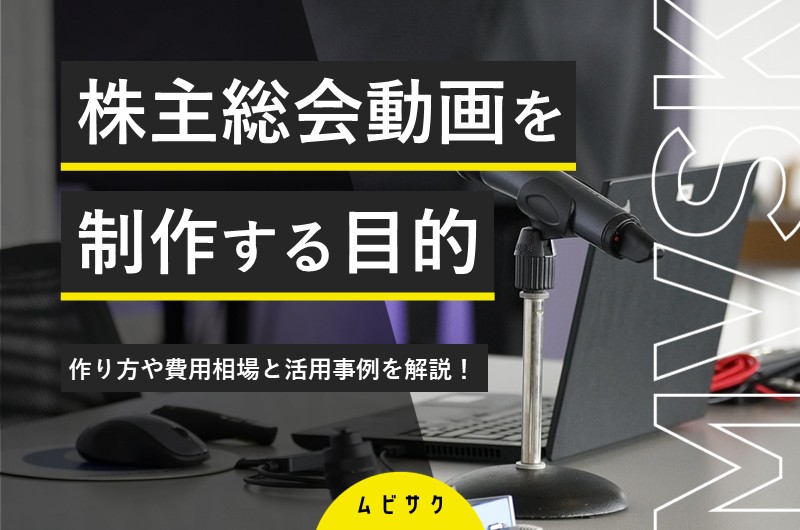
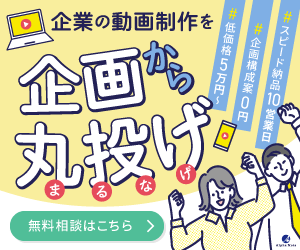


 03-5909-3939
03-5909-3939