インターネット環境が整い、スマホひとつで誰もが発信できる時代となった今、ライブ配信は企業や個人にとって重要な情報発信手段のひとつとして広がっています。従来の録画コンテンツとは異なり、配信者と視聴者がリアルタイムでつながり、コメントや質問を通じて双方向のコミュニケーションを取れる点が大きな魅力です。
しかし一方で、手軽さゆえに炎上やトラブルのリスクも伴うため、正しい理解と準備が欠かせません。本記事では、ライブ配信の特徴や生配信・オンデマンド配信との違い、メリット・デメリット、実際の始め方や必要な機材について解説します。
動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、ライブ配信やオンデマンド配信に活用できるセミナー動画の豊富な制作実績があります。動画制作を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。
ムビサクのセミナー動画の制作について詳しく知りたい方はこちら
- ライブ配信のメリットデメリット
- ライブ配信のやり方と流れ
- ライブ配信に必要な機材とアプリやSNSの選び方
目次
動画制作でこんなお悩みありませんか?
- 動画制作を考えているがどうすればよいかわからない
- 急いで動画を作りたいが方法がわからない
- 高品質な動画を制作したいが自社では難しい…
\ スピーディーに高品質な動画を作るならムビサク /
無料で相談・問い合わせるライブ配信とは?
ライブ配信とは、インターネットを通じて映像や音声をリアルタイムに届ける方法のことを指します。従来の録画コンテンツは編集や加工を経て公開されますが、ライブ配信は進行している様子をそのまま視聴者に届けられる点が特徴です。
例えば、イベントの様子やセミナーの講演を配信することで、現地に足を運べない人でも臨場感を持って参加できます。さらに、コメント機能を活用することで配信者と視聴者がその場でやり取りできるため、一方的に発信するだけでなく双方向のコミュニケーションを生み出せるのも魅力といえるでしょう。
ライブ配信と生配信の違い
ライブ配信と生配信は同じ意味を持つ言葉ですが、ニュアンスに違いがあります。一般的に「ライブ配信」はインターネット上でリアルタイムに発信することを指します。
一方で「生配信」は日本語独特の言い回しで、「生の声をそのまま届ける」という感覚が強調されます。ただし、テレビ番組では「生放送」や「生中継」という言葉が一般的に使われることが多く、「生配信」という言葉はYouTubeやTikTok、InstagramなどのSNSでよく用いられます。即時性やリアリティをより強く印象付けています。そのため、媒体によって言い回しを使い分けることが大切です。
ライブ配信とオンデマンド配信の違い
ライブ配信とオンデマンド配信の違いは、視聴のタイミングにあります。ライブ配信は決められた時間にリアルタイムで視聴する必要があり、臨場感やその場の一体感を味わえるのが特徴です。
一方、オンデマンド配信は録画されたコンテンツを視聴者が好きな時間に再生できるため、時間や場所を選ばず利便性が高いといえます。例えば、スポーツの試合をライブ配信で見ると興奮を共有できますが、後日オンデマンド配信で見返すとプレーをじっくり確認することが可能です。
なお、オンデマンド配信については、こちらの記事も参考にしてください。
ライブ配信が10代・20代に人気の理由

ライブ配信が10代・20代に人気の理由として、以下のような点があげられます。
- TikTokやInstagramなどSNSの普及
- 5GやWi-Fiなど通信環境の整備
- インフルエンサーなど新たな収益化の普及
ここでは、それぞれの理由や背景について詳しく解説します。
TikTokやInstagramなどSNSの普及
ライブ配信が若い世代に人気を集めている背景には、SNSの普及が関わっています。特にTikTokやInstagramは動画を中心としたコミュニケーションが定着しており、手軽に配信や視聴を楽しめる環境が整っています。
例えば、友人の日常をInstagramのライブで共有したり、好きなアーティストのパフォーマンスをTikTokで体験したりすることで、距離を感じさせない交流が盛んです。こうしたSNSの特性はリアルタイム性を重視する若い世代と相性がよく、気軽に参加できる点がライブ配信の普及の要因となっています。
5GやWi-Fiなど通信環境の整備
ライブ配信が広く利用されるようになった背景には、通信環境の向上も大きな役割を果たしています。5Gの普及やWi-Fiの高速化によって、大容量の映像データでも途切れることなく配信や視聴が可能になり、ストレスを感じにくい環境が整いました。
例えば、これまでは高画質の動画をリアルタイムで配信すると途中で映像が止まることもありましたが、現在ではスムーズに映像と音声を届けられます。そのため、安定した通信基盤があることで、利用者は安心してライブ配信を楽しめるようになり、若い世代を中心に利用の幅が広がっているのです。
インフルエンサーなど新たな収益化の普及
10代や20代にライブ配信が浸透している理由のひとつに、インフルエンサーの活躍や収益化の仕組みの広がりがあります。ライブ配信では投げ銭機能(スーパーチャット)やスポンサー契約といった収益モデルが確立し、個人でも収入を得られる可能性が高まりました。
例えば、趣味で始めた配信がきっかけで多くのフォロワーを獲得し、企業からの広告案件につながるケースもあります。このように自己表現と収益化を両立できる点は、将来を模索する若い世代にとって魅力的です。そのため、単なる娯楽にとどまらず、自己実現やキャリア形成の手段のひとつとしてライブ配信が選ばれているのです。
ライブ配信のメリット

ライブ配信のメリットとして、以下のような点があげられます。
- コメントや質問でコミュニケーションがとれる
- 編集の必要がなく手軽に始められる
- 視聴者からの信頼性の向上や親近感につながる
ここでは、それぞれのメリットやライブ配信の効果について詳しく解説します。
コメントや質問でコミュニケーションがとれる
ライブ配信のメリットは、配信者と視聴者が同じ時間を共有しながら直接コミュニケーションを取れる点にあります。配信中に寄せられたコメントや質問にその場で反応することで、双方向の交流が生まれ、参加している感覚を高めることができます。
例えば、アーティストがライブ中にファンからの質問に答えたり、講師がセミナーで視聴者の意見を拾い上げたりすることで、一方通行の情報発信とは異なる関係性を築けます。こうしたやり取りは、視聴者にとって特別感を与え、配信者への関心や継続的な参加意欲を高める要因となります。
編集の必要がなく手軽に始められる
ライブ配信は録画動画と異なり、事前に編集作業を行う必要がなく、そのままの形で発信できる手軽さがメリットです。特別なスキルや複雑な準備が不要で、スマホとアプリさえあればすぐに配信を始められるため、多くの人にとって挑戦しやすい環境が整っています。
例えば、商品紹介を店舗からそのまま配信したり、日常の出来事をリアルタイムで共有したりと、状況に応じて柔軟に発信できるのも魅力です。編集がいらない分、時間やコストを抑えながら情報を届けられる点は、企業や個人にとって大きなメリットといえるでしょう。
視聴者からの信頼性の向上や親近感につながる
ライブ配信はリアルタイムで進行するため、配信者の姿や発言が編集を経ずにそのまま伝わり、視聴者にとってより自然で身近な印象を与えます。飾らない姿を見せることは、信頼感や親近感を高める効果につながります。
例えば、配信中に予期せぬハプニングが起こっても、対応の仕方や人柄が視聴者に伝わり、かえって好感を持たれることがあります。こうしたリアルなやり取りは、視聴者が配信者を身近に感じるきっかけとなり、単なる情報発信にとどまらず長期的な関係づくりに役立ちます。結果として、継続的なファンや顧客の獲得にもつながっていくでしょう。
ライブ配信のデメリット

ライブ配信のデメリットとして、以下のような注意点があります。
- ささいな発言で炎上のリスクがある
- 通信障害などのトラブルがある
- 事前集客をしないと視聴されづらい
ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
ささいな発言で炎上のリスクがある
ライブ配信のデメリットは、リアルタイムで進行するため、配信者の言葉や態度がそのまま視聴者に届いてしまう点です。その場の雰囲気で発した何気ない発言や表情が、意図せず誤解を招き炎上につながることもあります。
例えば、軽い冗談のつもりで口にした一言が差別的だと受け取られて批判を浴びたり、無意識の行動がマナー違反と指摘されたりする場合があります。録画された動画のように編集で修正できないため、一度配信されると取り消しが難しい点もリスクです。そのため、発言には注意を払い、視聴者にどのように受け止められるかを意識する姿勢が求められます。
通信障害などのトラブルがある
ライブ配信は安定した通信環境が前提となるため、回線の不具合や機材トラブルによって進行が妨げられる懸念もデメリットです。例えば、配信中に映像や音声が途切れてしまうと、視聴者は集中できず途中で離脱してしまうことがあります。
特に、大切なイベントや告知を行う際には、配信の質が信頼性にも直結するため、こうした問題は配信者にとって大きな不安要素となるでしょう。また、視聴者側の環境によっても見え方が異なるため、配信者が完全にコントロールできない部分がある点も注意が必要です。そのため、事前に配信テストを重ねるなどの準備が大切です。
事前集客をしないと視聴されづらい
ライブ配信はリアルタイムで行われるため、事前に告知や集客を行わなければ視聴者が集まらず、配信の効果を十分に得られない場合があります。例えば、SNSでの告知をせずに突然配信を始めても、視聴者が配信の存在に気づかず、再生数が伸びないことがあります。
録画された動画と違って後から検索して視聴されるケースが少ないため、開始前にターゲットに向けて情報を伝える工夫が求められます。配信内容の魅力だけでなく、配信時間の選び方や告知方法も成功を左右する要素となるため、計画的な準備が欠かせません。
ライブ配信のやり方と流れ

ライブ配信のやり方は以下のような手順で進みます。
- step1:ライブ配信をする目的と目標を定める
- step2:コンテンツを企画する
- step3:ターゲットへ告知する
- step4:撮影場所の手配とリハーサルをする
- step5:アプリやSNSで配信する
ここでは、それぞれの手順について具体的に紹介します。
step1:ライブ配信をする目的と目標を定める
ライブ配信を始める際には、まず目的と目標を明確にすることが大切です。何のために配信するのかを定めておかないと、内容にまとまりがなくなり視聴者に伝わりにくくなります。
例えば、新商品の認知度を高めたいのか、既存顧客との関係を深めたいのかによって、配信の進め方や発信する内容が変わります。また、目標数値を設定することで効果を測定しやすくなり、次回以降の改善につなげることも可能です。目的と目標をはっきりさせておくことで、配信全体の方向性が定まり、視聴者にとってもわかりやすい内容になります。
step2:コンテンツを企画する
決まった目的と目標に沿って、コンテンツを企画していきましょう。配信内容は視聴者の関心を引きつけるものでなければならず、事前の構成を考えることでスムーズに進行できます。
例えば、商品紹介のライブであれば、特徴を伝えるだけでなく実演や質問の時間を盛り込むと効果的です。また、教育系の配信ではスライド資料を用意することで理解度を高められます。コンテンツの企画段階でストーリー性や時間配分を考えておくと、配信中のトラブルや間延びを防ぐことができ、視聴者にとっても集中しやすい時間となるでしょう。
step3:ターゲットへ告知する
ライブ配信はリアルタイムでの視聴が前提となるため、事前にターゲットへ告知することが欠かせません。SNSやメールを使って配信日時や内容を知らせることで、参加の意欲を高めることができます。
例えば、Instagramのストーリーズでカウントダウンを設置したり、Twitterで告知ツイートを繰り返したりすると効果的です。また、ターゲットに合わせた媒体を選ぶことも重要で、若年層にはSNS、ビジネス向けにはメールやウェビナー告知サイトが適しています。十分な告知を行うことで、より多くの視聴者にリアルタイムで参加してもらえる環境を整えられます。
なお、ターゲットへの告知として、ティザー動画を用いることもあります。ティザー動画については、こちらの記事も参考にしてください。
step4:撮影場所の手配とリハーサルをする
安定したライブ配信を行うには、撮影場所の環境を整えることが欠かせません。照明や音響、背景などが適切でないと、配信の質が下がり視聴者の満足度に影響します。
例えば、静かな会議室を利用する場合でも、反響音を防ぐ工夫や明るさを調整することが必要です。さらに、本番前にリハーサルを行うことで機材の動作確認や進行の流れをチェックでき、不測のトラブルを防げます。事前に環境を整えてリハーサルを重ねることは、安心感を持って配信を行うための重要な準備といえるでしょう。
step5:アプリやSNSで配信する
準備が整ったら、いよいよ実際にアプリやSNSを使って配信を行います。配信するプラットフォームは目的やターゲット層に応じて選ぶことが大切です。例えば、若年層を中心にアプローチしたい場合はTikTokやInstagramが適しており、ビジネス向けにはYouTubeやZoom(ウェビナー)を利用すると効果的です。
配信開始後はコメント機能を活用して視聴者と交流し、リアルタイムで反応を取り入れることで参加意識を高められます。また、配信が終了した後にアーカイブを残せば、リアルタイムで参加できなかった視聴者にも情報を届けることができ、配信の効果が期待できるでしょう。
なお、ウェビナーのメリットについては、こちらの記事も参考にしてください。
ライブ配信に必要な機材と事前準備

ライブ配信に必要な機材として、以下のようなものを事前に用意しておきましょう。
- スマホ・カメラ
- マイク(ピンマイク)
- 三脚・スタンド
- 照明(リングライト)
ここでは、それぞれの機材の選び方や役割を具体的に解説します。
スマホ・カメラ
ライブ配信を始める際にまず必要となるのが映像を映すための機材で、スマホやカメラが基本となります。現在のスマホは高画質での撮影機能が備わっており、特別な機材を用意しなくても十分に配信を行うことができます。
例えば、個人配信ではスマホを使って手軽に始められますが、企業イベントや商品発表会では一眼レフやビデオカメラを使用することで、より鮮明で安定した映像を届けられます。用途や目的に合わせて機材を選ぶことで、視聴者にとって見やすく信頼性のある配信を実現できます。
マイク(ピンマイク)
映像と同じくらい重要なのが音声であり、マイクの選び方によって配信の印象は大きく変わります。内蔵マイクだけでは雑音を拾いやすいため、クリアな音を届けるには専用のマイクを用意することが望ましいでしょう。
例えば、話者が動きながら説明する場合にはピンマイクを使うと、声が安定して拾われ聞き取りやすさが向上します。固定のトーク形式であればスタンドマイクやガンマイクもおすすめです。音声は視聴者の集中度に直結するため、映像のクオリティ以上に重要視される場合もあります。そのため、適切なマイクを使うことで、配信の信頼性を左右するともいえるでしょう。
三脚・スタンド
安定した映像を届けるには、三脚やスタンドの使用が欠かせません。手持ちで撮影すると画面が揺れてしまい、視聴者にとって見づらくなることがあります。三脚やスタンドを使えば長時間の配信でも安定感を保て、映像に安心感を与えることができます。
例えば、スマホを固定できる小型三脚を利用すれば、自宅やオフィスでも手軽に配信環境を整えられます。また、企業イベントやセミナーのように広い範囲を撮影する場合は、高さ調整が可能なスタンドを活用することで会場全体を映し出すこともできます。
照明(リングライト)
映像をより見やすくするためには照明の工夫も必要です。暗い環境で配信すると表情が伝わりにくく、視聴者の集中を妨げる可能性があります。そのため、リングライトのように均一な光を当てられる照明を使用することで、顔色や商品の様子を鮮明に映し出せます。
例えば、自宅やオフィスで配信する場合でも、リングライトを設置するだけで雰囲気が明るくなり、映像の印象が大きく変わります。また、自然光が得られる日中であっても、照明を組み合わせることで安定した映像になるため、照明の用意は大切です。
ライブ配信アプリやSNSの選び方とポイント

ライブ配信アプリやSNSの選び方とポイントとして、以下のような点を意識しましょう。
- ユーザー数の多いアプリやSNSを選ぶ
- 配信ジャンルと視聴者層で選ぶ
- 画質や通信速度の安定性で選ぶ
ここでは、それぞれの選び方のポイントを具体的に解説します。
ユーザー数の多いアプリやSNSを選ぶ
ライブ配信を始める際には、利用者の多いアプリやSNSを選ぶことが重要です。ユーザー数が多いプラットフォームほど配信が届く可能性が高まり、新しい視聴者との出会いにもつながります。
例えば、InstagramやTikTokは若い世代の利用が多く、エンタメ性のある配信に適しています。一方、YouTubeは幅広い世代に利用され、検索性も高いため長期的に視聴されやすいのが特徴です。このように利用者規模の大きさは、配信の目的やターゲットに直結する要素となるため、自社に合った場を選ぶことが成果につながります。
配信ジャンルと視聴者層で選ぶ
配信する内容や対象となる視聴者層に合わせてアプリやSNSを選ぶこともポイントです。ジャンルによって適したプラットフォームは異なり、特性を理解することで効果的に届けられます。
例えば、趣味や日常を共有したいならカジュアルさのあるInstagramやTikTokが向いており、学習やビジネスに関する情報を発信するならYouTubeやZoom(ウェビナー)が適しています。視聴者がどこで情報を得ているかを考慮すれば、配信が届く可能性は高まるため、配信内容と利用者層を照らし合わせて選ぶことが大切です。
画質や通信速度の安定性で選ぶ
ライブ配信の印象を左右するのが、画質や通信速度の安定性です。どんなに魅力的な内容でも、映像が乱れたり音声が途切れたりすると視聴者は離れてしまいます。そのため、利用するアプリやSNSがどの程度の画質や通信に対応しているかを確認することが欠かせません。
例えば、イベントを高画質で届けたい場合には、フルHDや4K配信に対応したサービスを選ぶのが適切です。また、安定した通信環境に強みを持つプラットフォームであれば、長時間の配信でも安心できます。
なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、ライブ配信後のオンデマンド配信に効果的な動画の豊富な実績があります。
無料相談も承っていますので、ぜひ一度ご連絡ください。
ライブ配信のよくあるご質問
ライブ配信についてのご質問はかなり多くいただきます。その中から、頻度の高いものへの回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
ライブ配信とは何ですか?
- ライブ配信とは、インターネットを利用して映像や音声をリアルタイムで届ける方法です。録画された動画のように編集を行わず、その場で起きている出来事をそのまま視聴者に伝えられる点が特徴です。イベントやセミナーの様子を配信すれば、現地に来られない人でも臨場感を共有でき、同じ時間を体験できる魅力があります。
ライブ配信と生配信の違いは何ですか?
- ライブ配信と生配信は基本的には同じ意味ですが、使われ方に違いがあります。「ライブ配信」はネットを通じた発信を表す際に用いられることが多いです。一方で「生配信」は日本語特有の言い回しで、「生の声や姿をそのまま届ける」ニュアンスを強調します。テレビでは「生放送」や「生中継」と呼ばれるのが一般的です。
ライブ配信でNGな行為は何ですか?
- ライブ配信では、視聴者を不快にさせる発言や差別的な言葉、暴力的な表現などは避けなければなりません。例えば、冗談のつもりで口にした一言が誤解され、大きな批判につながることもあります。また、著作権を侵害する音楽や映像を無断で使用する行為も禁止されており、配信者の信用や安全性を損なうリスクを伴います。
まとめ

ライブ配信は、配信者と視聴者が同じ時間を共有しながら交流できる点が特徴で、企業や個人にとって有効な発信手段として広がっています。メリットとしては双方向のコミュニケーションや手軽さ、信頼性の向上があげられます。一方で、炎上や通信トラブル、集客不足といったデメリットも存在します。こうした特性を理解し、目的に合わせて適切な準備や機材、プラットフォームを選ぶことで、ライブ配信は効果的な手段となるでしょう。
なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、ライブ配信後のオンデマンド配信に効果的な動画の豊富な実績があります。
無料相談も承っていますので、ぜひ一度ご連絡ください。

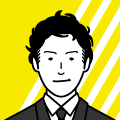

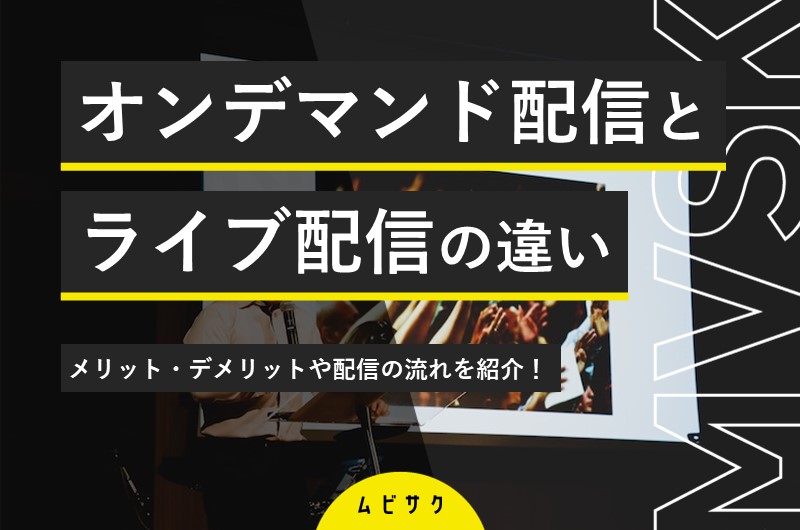
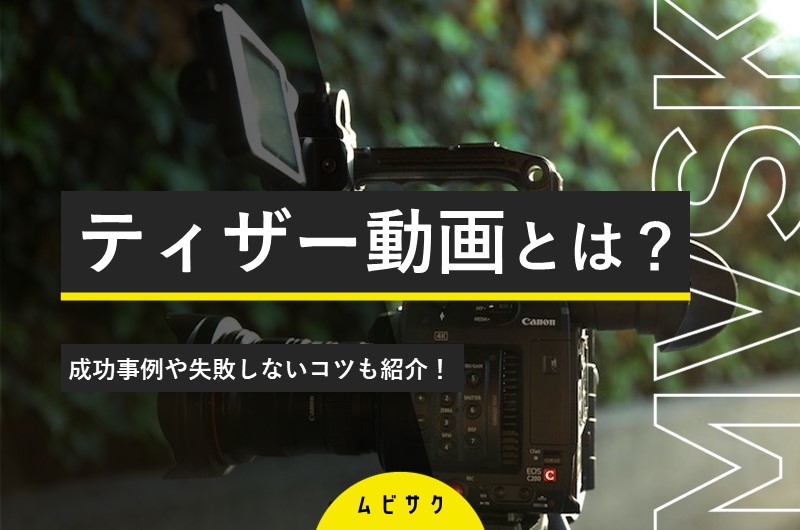


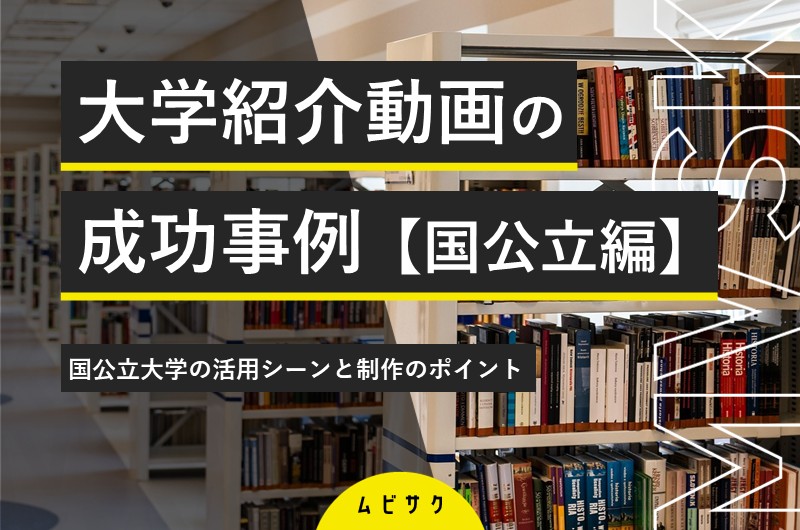
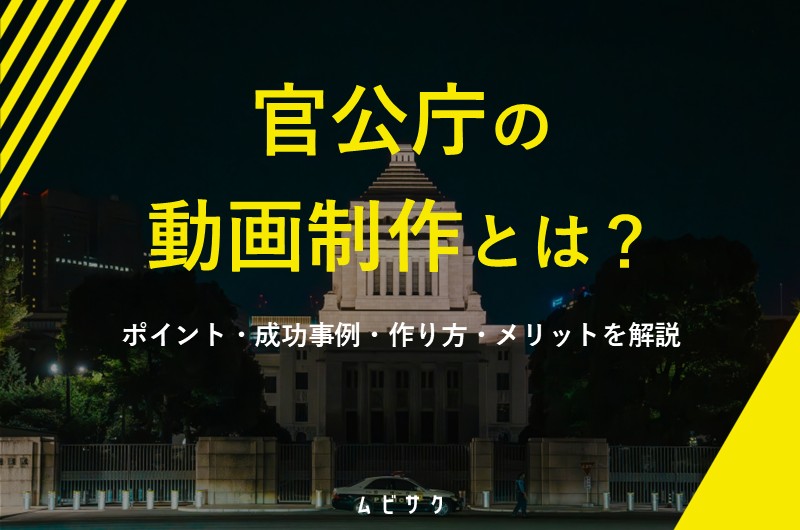
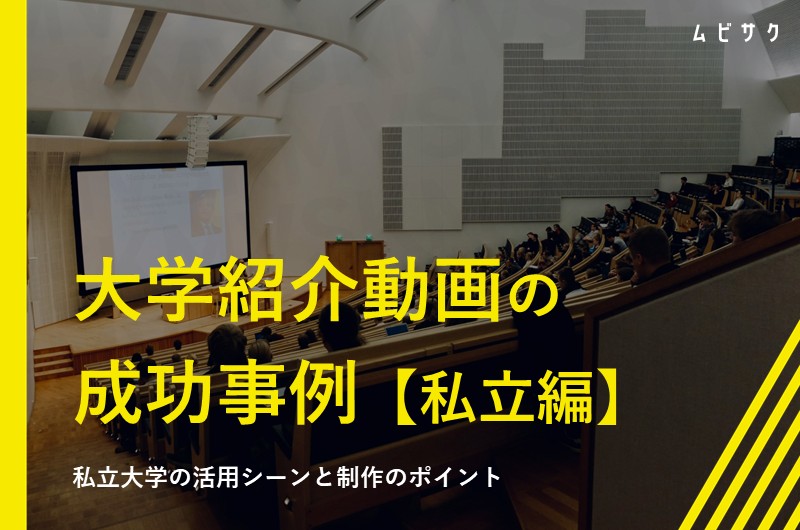

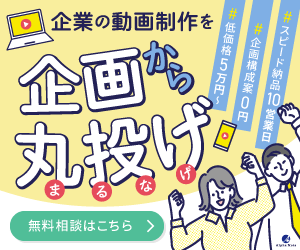


 03-5909-3939
03-5909-3939