動画制作・映像制作を依頼する際、多くの企業や担当者の方が最初に直面するのが「契約書」の取り扱いです。魅力的な動画・映像を制作することばかりに意識が向きがちですが、契約内容を曖昧にしたまま進めてしまうと、後から予期せぬトラブルが生じる可能性があります。
また、著作権や利用権をめぐる誤解があれば、動画・映像公開後に思わぬリスクを背負うこともあります。本記事では、動画制作・映像制作の契約書において特に注意すべきポイントをプロの視点で解説し、さらに実務で使える契約書テンプレートもご紹介します。
動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、動画制作の豊富な実績があります。動画制作を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。
ムビサクの動画制作・映像制作サービスについて詳しく知りたい方はこちら
- 動画制作・映像制作で契約書を作成しないリスク
- 動画制作・映像制作の契約書の記載項目と注意点
- 動画制作・映像制作における契約書の読み方・書き方のポイント
目次
動画制作でこんなお悩みありませんか?
- 動画制作を考えているがどうすればよいかわからない
- 急いで動画を作りたいが方法がわからない
- 高品質な動画を制作したいが自社では難しい…
\ スピーディーに高品質な動画を作るならムビサク /
無料で相談・問い合わせる動画制作・映像制作の契約書とは?
動画制作・映像制作の契約書とは、依頼者と制作会社の間で取り決めた内容を明確にし、後々の誤解やトラブルを防ぐために交わされる文書です。制作の流れや成果物の範囲、支払い条件や著作権その他の知的財産権の扱いなど、双方が合意した事項を具体的に記載することで安心してプロジェクトを進行できます。
例えば、成果物の修正対応の回数や追加費用の発生条件を事前に明示しておけば、制作中に想定外の負担が発生することを避けられます。契約書は単なる形式的な書面ではなく、依頼者と制作者の信頼関係を築く基盤となるものであり、動画制作・映像制作のプロジェクトを円滑に進めるために欠かせない役割を担っています。
動画制作・映像制作で契約書を作成しないリスク

動画制作・映像制作で契約書を作成しないリスクとして、以下の点を心得ておきましょう。
- 支払時期のトラブルを防ぐ
- 修正回数や納期の認識の齟齬を防ぐ
- 著作権や利用権の抵触を防ぐ
ここでは、それぞれのリスクについて具体的に解説します。
支払時期のトラブルを防ぐ
契約書を作成しないまま進めてしまうと、料金の総額や支払時期について双方の認識がずれてしまうことがあります。例えば、制作会社は納品後すぐの支払いを想定している一方で、依頼者は翌月末の支払いと考えていた場合、支払時期をめぐるトラブルが生じるかもしれません。
契約書に支払時期を明確に記載しておけば、どのタイミングで、料金を支払うのかが双方にとって共通の基準となります。あいまいさを残さず取り決めを明示することは、信頼関係を保ちながらプロジェクトを進めるための大切な手段といえます。
修正回数や納期の認識の齟齬を防ぐ
制作過程でよく起こるのが修正回数や納期をめぐる行き違いです。例えば、依頼者は成果物が一定の品質等に至るまで数回の修正対応を当然と考えていても、制作会社は一度の修正対応のみを前提にしていた場合、追加費用の発生をめぐるトラブルが生じるかもしれません。
また、納期についても「月末まで」と「月末営業日まで」といった解釈の差がトラブルの元となることがあります。契約書に修正回数や納期を具体的に記載しておくことで、事前に認識を合わせられ、後からの不必要な衝突を避けることができます。
著作権や利用権の抵触を防ぐ
動画・映像には企画や素材、音楽など多くの著作物その他の権利物が関わるため、権利関係を明確にしておかないと後のトラブルにつながります。例えば、完成した動画を依頼者が自由に編集して二次利用したいと考えても、制作会社が二次利用を認めていなければ、利用制限をめぐるトラブルが生じるかもしれません。
また、権利関係を曖昧にしておくと、意図せず第三者の権利を侵害する危険も否定できません。契約書に著作権の帰属や利用可能な範囲を具体的に記載しておけば、双方が安心して動画・映像を活用でき、余計な不安を抱えずに済むようになります。
【テンプレート】動画制作・映像制作の契約書の記載項目と注意点
動画制作・映像制作の契約書の記載項目として、以下のような点があげられます。
- 納期・納品形式
- 支払期日・支払方法
- 著作権・知的財産権
- 秘密保持義務
- 免責事項
ここでは、それぞれの記載項目についてテンプレートとともに注意点を解説します。なお、ここで紹介する記入例は、ムビサクの契約書とは異なり、あくまでもテンプレートである点にご注意ください。
納期・納品形式
動画制作・映像制作において納期や納品形式は、依頼者と制作会社双方にとって重要な確認事項です。例えば「月末納品」と一言で表現しても、依頼者は納期最終日の自らの営業時間中を想定し、制作会社は納期最終日当日中を想定するなど解釈が異なる場合があります。
また、どのようなファイル形式、かつ、どのような方法で納品するのか(例えば、DVDやクラウドストレージを利用する等)といった納品形式の違いも、後から混乱を招きやすい要素です。契約書に具体的な日付や時間、納品形式を記載しておけば、納品の基準が明確化され、想定外の行き違いを防止できます。
納期・納品形式のテンプレート(記入例)
乙は成果物を〇年〇月〇日(〇時)までに、MP4(H.264)形式のデータとしてクラウド共有リンクに格納した上で、当該クラウド共有リンクを甲に通知することで納品する。甲は納品後〇営業日以内に成果物の検査を行い、契約不適合がある場合は〇回に限り乙に修正を依頼できる。甲が検査期限内に通知しないときは検査に合格したものとみなす。
支払期日・支払方法
料金の支払いに関する取り決めは、契約トラブルを避けるために欠かせません。例えば、依頼者が「納品後30日以内」と認識しているのに対し、制作会社は「翌月末払い」を想定していた場合、支払いの遅延や請求の食い違いが生じかねません。
さらに、支払方法が銀行振込なのか、その他の方法なのか、また一括払いなのか、分割払いなのかを明記しないと、実務上の混乱を招くことがあります。契約書には支払期日や支払方法を具体的に書き込み、請求書の発行時期や延滞時の対応も併せて定めておくことで、双方が安心してやり取りできる環境を整えられます。
支払期日・支払方法のテンプレート(記入例)
乙は納品完了後に請求書を発行し、甲は請求書発行日の翌月末日までに乙指定口座へ振り込む。請求書に別途期日の記載がある場合は当該期日を優先する。支払期日を経過した場合、甲は完済まで年〇%の割合で延滞金を支払うものとする。
著作権・知的財産権
動画には映像や音楽、ナレーションなど多くの著作物その他の権利物が含まれるため、取り扱いは契約書で明確にする必要があります。例えば、依頼者は完成した動画を自由に改変できると思っていても、制作会社が権利移転・利用許諾していなければ、後に利用制限を巡って対立が生じる可能性があります。
また、既存の音源や画像を利用する場合、第三者の権利に抵触しないかどうかも重要な確認点です。著作権等の権利を誰が保有し、どの範囲で利用許諾されているかを契約書に記載しておけば、安心して動画・映像を公開し、広く活用することが可能になります。
著作権・知的財産権のテンプレート(記入例)
成果物の著作権(著作権法27条・28条の権利を含む。乙が著作権を有するものに限られる。)は、甲が料金を全額支払った時点で、乙から甲に移転する。乙は著作権の移転後、著作者人格権を行使しない。料金全額支払前の利用は乙の書面承諾がある場合に限り、本契約の目的達成に必要な範囲で許される。既存著作物の利用許諾は甲の責任と費用負担とする。
秘密保持義務
動画制作・映像制作の過程では、依頼者の事業戦略や未公開情報に触れることも少なくありません。例えば、新製品のPR動画を制作する際に公開前の情報が外部に漏れてしまうと、依頼者にとって損失となる可能性があります。
そのため、秘密保持に関する条項を契約書に盛り込むことは必須です。具体的には、制作過程で知り得た情報を第三者に漏らさないことや、契約終了後も一定期間は守秘義務が続くことを定めると安心です。こうした取り決めがあることで、依頼者は安心して必要な情報を提供でき、制作会社も責任を持って対応する姿勢を示せます。
秘密保持義務のテンプレート(記入例)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術・営業・財務・組織等の情報を秘密情報とし、第三者に開示・漏洩せず、本契約の目的以外に利用しない。委託先等へ開示する場合は本契約と同等の守秘義務を課す。自ら又は自らの委託先等で漏洩等が発生した又はおそれがあるときは直ちに相手方に通知し、相手方の指示に従う。
免責事項
予期せぬ事態に備えるため、免責事項の取り決めも契約書に欠かせません。例えば、天災や通信障害など不可抗力によって納品が遅れた場合、制作会社が無限に責任を負うのは現実的ではありません。
契約書においては、こうした状況下での責任範囲を明記することで、双方が納得の上で契約を進められます。また、依頼者の事情によって動画・映像の公開後にトラブルが発生した際、制作会社がどこまで関与するかを定めることも重要です。免責事項は、双方の立場を守りながら、予測できないリスクに備えるための仕組みといえます。
免責事項のテンプレート(記入例)
天災、停電、通信設備の障害・工事等の不可抗力に起因する委託業務の中断・遅延について、乙は責任を負わない。乙の過失(故意又は重過失を除く。)による損害賠償額の上限は委託業務の料金額とする。成果物に起因する甲又は甲の顧客と第三者間の紛争について、乙は責任を負わない。
動画制作・映像制作における契約書の読み方・書き方のポイント

動画制作・映像制作における契約書の読み方・書き方のポイントとして、以下のような点を意識しましょう。
- 修正回数や追加費用をチェックしておく
- 著作権や利用範囲を具体的に把握しておく
- キャンセル条件や免責事項も確認しておく
ここでは、それぞれのポイントについて具体的に紹介します。
修正回数や追加費用をチェックしておく
動画制作・映像制作の現場では、成果物の納品後に修正依頼が発生することが一般的です。 しかし、修正回数や追加費用の条件を契約書に明記していないと、依頼者と制作会社の認識が食い違い、余計な摩擦を生むことになります。
例えば、依頼者は数回の修正を含むと思っていても、制作会社は一度だけを前提にしていた場合、追加料金を巡るトラブルが起きかねません。こうした事態を防ぐためには「修正は1回まで料金に含まれる」「それ以降は1回ごとに追加費用を請求する」といった条項を明確にしておくことが重要です。契約段階で修正回数や追加費用の発生条件を明確化することは、双方が安心して制作に取り組むための前提条件となります。
著作権や利用範囲を具体的に把握しておく
映像には映像素材や音楽、ナレーションなど多くの著作物その他の権利物が関わるため、権利関係を契約書で具体的に定めておかないと後々の問題につながります。 例えば、依頼者が完成した動画を二次利用したいと考えても、著作権が制作会社に帰属している場合には自由に編集や再配布ができず、追加の契約が必要になるケースもあります。
契約書には著作権その他の権利物が誰に帰属するのか、利用できる範囲はどこまでか、商用利用や再編集が認められるかなどを明記しておくことが望ましいです。こうして具体的にルールを取り決めておけば、安心して動画を公開・活用することができ、不要なトラブルを回避できます。
キャンセル条件や免責事項も確認しておく
制作が進行してから依頼を取り消したい場合や、予期せぬ事態で納品が遅れる場合に備えて、キャンセル条件や免責事項を確認しておくことは欠かせません。 例えば、契約成立後に依頼者の都合でキャンセルした場合、制作会社は既に準備や作業を進めているため、その費用を補償するキャンセル料が発生します。
また、天災や通信障害など不可抗力で納品が遅れた際に責任をどう扱うかも、契約書に明記しておくと安心です。これらをあらかじめ取り決めておけば、想定外のトラブルが起きても冷静に対応でき、双方の立場を守ることにつながります。
動画制作・映像制作における契約書締結の流れ

動画制作・映像制作における契約書締結の流れは以下のステップで進みます。
- step1:契約内容を双方ですり合わせる
- step2:合意した内容に基づいて契約書を作成する
- step3:修正点を反映して締結する
ここでは、それぞれの契約書締結の流れを具体的に解説します。
step1:契約内容を双方ですり合わせる
契約書を作成する前段階として、依頼者と制作会社の間で契約内容を丁寧にすり合わせることが欠かせません。 例えば、納期の認識や修正回数の範囲、使用できる媒体などが双方で異なっていれば、後々大きな誤解を招きかねません。
打ち合わせでは、制作の目的や完成した成果物の利用シーンまで共有しながら、具体的に合意できる点を積み重ねることが大切です。こうして合意形成を行っておけば、その後に作成される契約書も明確になり、トラブルを防ぐだけでなく、信頼関係の構築にもつながります。
step2:合意した内容に基づいて契約書を作成する
すり合わせで合意した内容は、口頭だけでなく契約書という形に落とし込むことが必要です。 例えば、支払方法や納品形式を打ち合わせで確認していても、書面に記載がなければ後から「聞いていない」と認識が食い違う恐れがあります。
契約書には、料金や納期、修正回数、著作権その他の権利物の帰属といった基本事項を盛り込み、双方が同じ条件を参照できるようにします。また、曖昧な表現を避けて、誰が見ても解釈が一致する文言でまとめることが重要です。合意内容を契約書として可視化することで、実務における安心感が高まります。
step3:修正点を反映して締結する
契約書の草案ができたら、そのまま署名押印に進むのではなく、内容を再確認し修正点を反映させることが大切です。 例えば、依頼者が納期に関してより明確な日付を求める場合や、制作会社が追加費用の条件を補足したい場合など、双方の意見を適切に反映していく必要があります。
こうした修正はメールや電子署名サービスを利用してやり取りすれば効率的に進められます。最終的に双方が納得できる内容になった段階で署名することで、形式だけの契約ではなく実効性を持つ契約書となり、安心して制作を進めることが可能になります。
動画制作・映像制作の契約書を修正したい際の対応方法

動画制作・映像制作の契約書を修正したい際の対応方法として、以下のような点を意識しましょう。
- 修正点はどのように変えたいか具体的に整理する
- 双方の合意を得るために丁寧に申し入れる
- 弁護士などの専門家のチェックを入れる
- 修正内容は必ず文章に反映する
ここでは、それぞれの修正方法について具体的に解説します。
修正点はどのように変えたいか具体的に整理する
契約書を修正したいと思ったときには、漠然とした要望ではなく、どの部分をどのように変えたいのかを具体的に整理することが重要です。例えば「納期をもう少し柔軟にしたい」と考える場合でも、「〇月〇日から〇日延長してほしい」と明確にすれば、相手も判断しやすくなります。
支払い条件や修正回数の取り決めについても、現行条文をどのように修正したいのかを書き出しておくと、協議がスムーズに進みます。事前に自分の要望を具体的にまとめておくことで、無駄な行き違いを避け、相手に誠実さを伝えることにもつながります。
双方の合意を得るために丁寧に申し入れる
修正を希望する際には、一方的に条件を押し付けるのではなく、相手に理解を求めながら丁寧に申し入れることが欠かせません。例えば、追加費用の上限を変更したい場合に「この条件では難しい」とだけ伝えるのではなく、「予算計画の都合で上限を〇円にしたい」と理由を添えて説明することで、相手も納得しやすくなります。
修正は交渉の場であると同時に信頼関係を築く機会でもあるため、柔軟に歩み寄る姿勢が大切です。丁寧なコミュニケーションによって、双方が納得できる合意形成が実現できるでしょう。
弁護士などの専門家のチェックを入れる
契約書を修正する際には、当事者同士だけで判断するのではなく、法律の専門家にチェックを依頼することもおすすめです。例えば、著作権の帰属やキャンセル料の条件といった条項は、条文の表現によって解釈が変わる場合があり、思わぬリスクを抱えることがあります。
弁護士などの専門家であれば、依頼者と制作会社双方の立場を踏まえつつ、法的に問題のない形へと整えてくれます。少し手間に感じても、専門的な視点を取り入れることで安心感が増し、後にトラブルが生じた際にも強い契約書にすることが可能になります。
修正内容は必ず文章に反映する
協議によって合意した修正点は、必ず契約書の文章に反映させることが必要です。例えば、打ち合わせの場で「修正回数を1回までとする」と口頭で決めても、契約書に明記しなければ、後で「正式な取り決めではなかった」と主張される恐れがあります。
メールのやり取りで合意を確認するだけでなく、最終的には契約書の条文を修正し、双方が署名や押印を行うことが大切です。書面に残しておくことで、後から条件を確認でき、紛争防止の確かな証拠にもなります。合意事項を形式化することが信頼関係を守るための基本です。
なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、目的や用途にあわせた動画制作の豊富な実績があります。
無料相談も承っております。ぜひ一度ご連絡ください。
動画制作・映像制作の契約書におけるよくあるご質問
動画制作・映像制作の契約書についてのご質問はかなり多くいただきます。その中から、頻度の高いものへの回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
動画制作・映像制作の契約書の基本構成は何ですか?
- 動画制作・映像制作の契約書の基本構成には、納期、納品形式、支払条件、期日、著作権、利用範囲、秘密保持義務、免責事項などが含まれます。項目を整理して書き込むことで、成果物の完成までの流れを双方が共通認識として持つことが可能です。その結果、想定外のトラブルや誤解を防ぎ、信頼関係を維持できます。
動画制作・映像制作の契約書を作成するときのルールは何ですか?
- 契約書を作成するときの基本的なルールは、曖昧な表現を避け、双方が同じ理解を持てるように具体的に記載することです。修正回数や支払期日、納品形式も数値や方法を正確に示すことが大切です。こうした具体性のある取り決めによって、契約が安心して履行され、双方が納得できる契約書となるでしょう。
動画制作・映像制作の契約書は甲乙どちらが作成しますか?
- 契約書は依頼者(甲)と制作会社(乙)のどちらが作成しても構いませんが、実務上は制作会社である乙がひな型を提示し、依頼者が内容を確認するケースが多いです。乙が提出した契約書案に対し、甲が要望を加えて再度調整する流れが一般的です。重要なのは一方的に決めるのではなく、双方の合意に基づいて決定することです。
まとめ

動画制作や映像制作の契約書は、単なる形式的な書面ではなく、依頼者と制作会社の双方を守るための重要な役割を担います。例えば、修正回数や支払い条件を曖昧にしたまま進めれば、思わぬ誤解や負担が発生しかねません。
著作権や利用範囲についても、具体的に取り決めておくことで安心して成果物を活用できます。本記事で紹介した注意点やテンプレートを活用すれば、契約書をより実務的で信頼性のあるものに整えることができるでしょう。しっかりと契約内容を確認し合意を文章化することが、円滑で安心な動画制作・映像制作につながります。
なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、目的や用途にあわせた動画制作の豊富な実績があります。
無料相談も承っております。ぜひ一度ご連絡ください。

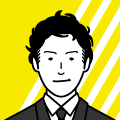
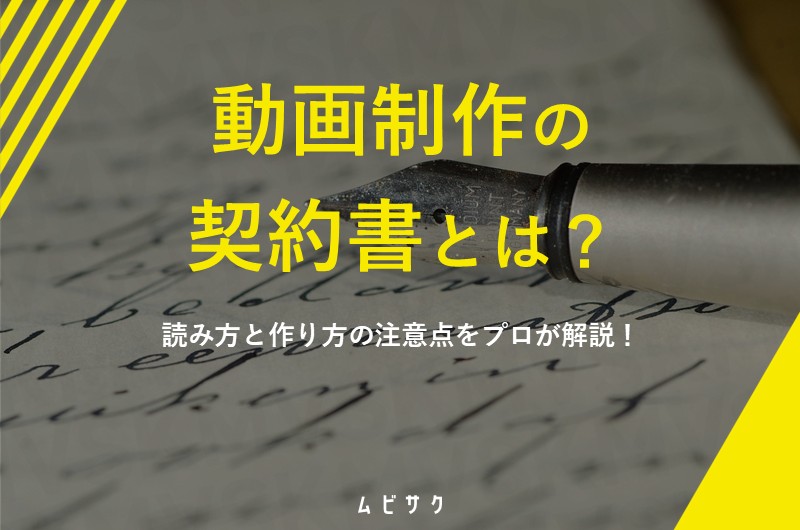

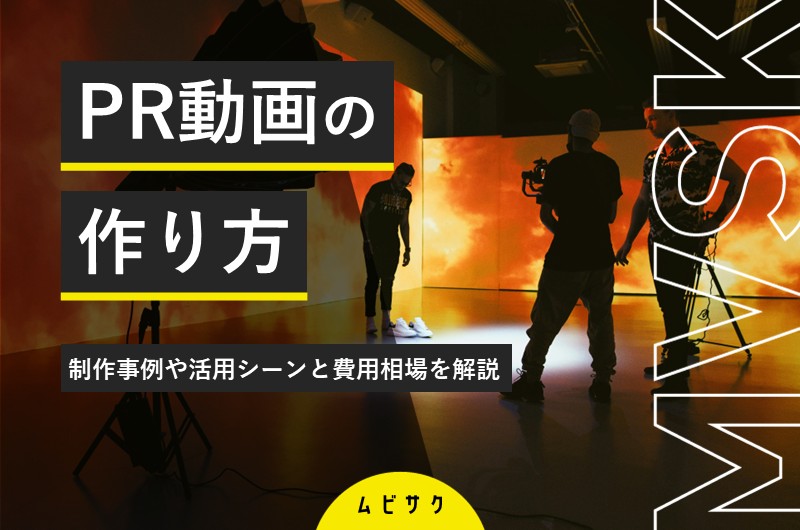

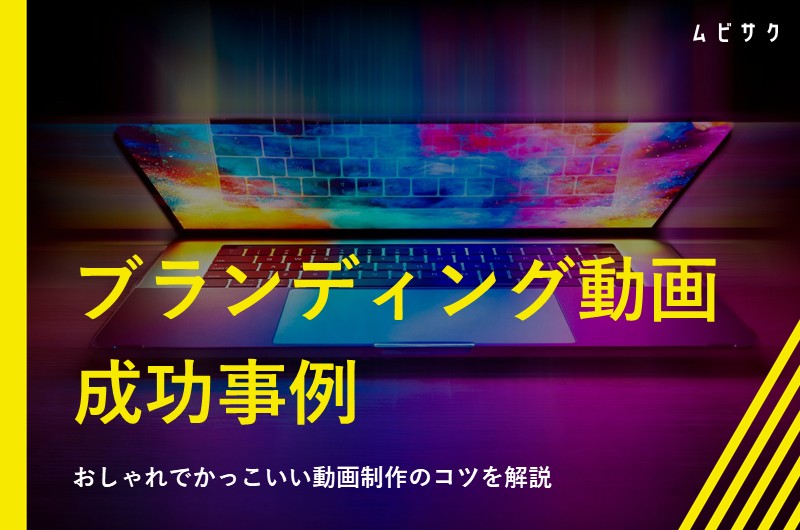
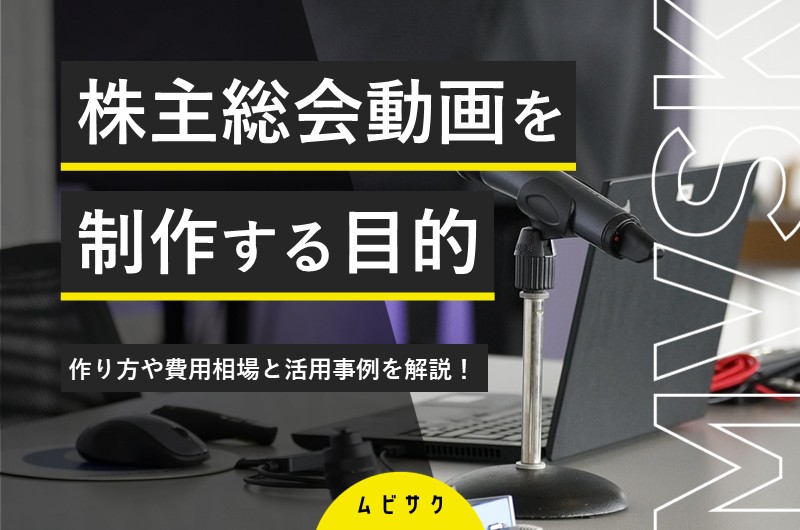
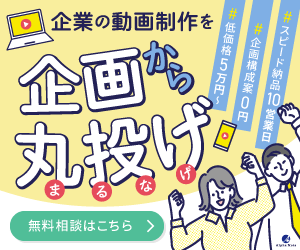

 03-5909-3939
03-5909-3939